





|
2004.05【特集記事−本誌編集部より−】 進化するトヨタ生産システム 関根憲一(付加価値経営研究所所長)
|
||
I.最新のトヨタ生産方式最近トヨタ生産方式を再度勉強するため2カ月に1回位の割合でトヨタの関連企業、協力工場を「見たり、聞いたり、たずねたり」して勉強している。思いつくままに最新のトヨタ生産方式をメモしてみると、
II.昔のトヨタ、今のトヨタまず、表1を見て、昔のトヨタと今のトヨタを項目ごとに対比してほしい。昔のトヨタとは昭和35年頃の元町工場、今のトヨタとは、2004年現在の田原工場、九州工場を意味する。約40年間の進化を数字であらわしたのが表1-1である。 工場の生産性をあらわすものさしは、いろいろあるが、最もわかりやすいのは、製造のリードタイム(以下・LTという)である。早くつくればよいものが、安く出来、儲かるからである。 昔のトヨタはヨコ持ち(機械の種類別レイアウト)だったので、LTは約50日かかっていた。エンジンの「からし」をいれると75日。今はすべてがタテ持ち(工程の流れに従ったレイアウト)になったので、35,000点のセルシオでも、42H、クラウンは34Hという。約1/50に進化している。 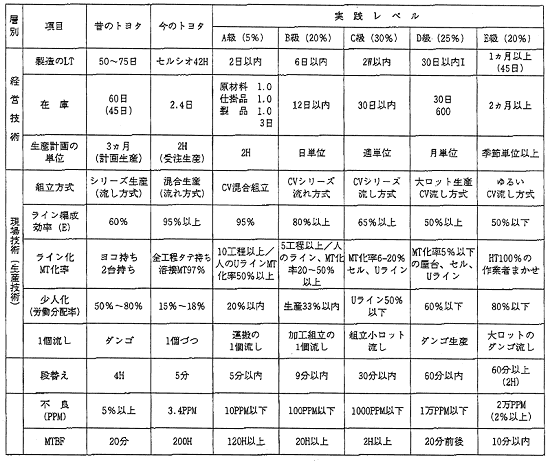 成立条件の第1は 1.LT1/50化の技術プレス、鍛造、熱処理、機械加工、溶接、塗装、組立、検査工程を連結して一貫ラインにする。あたかも装置工場みたいなラインをつくる。LAYOUTを思い切って改善す る。「タテ(縦)持ち」の思想から、 らゆる工程を連結していく行動力である。しかも、1人1人の生産技術者にタテ持ちの思想が浸透している点である。例えば、O工場では機械加工ラインに鍛造設備はもちろん、ゴムの加流工程や高周波の焼き入れまでは組み入れる。そうするとLT(P)の短縮化(R)は次式のようになる。 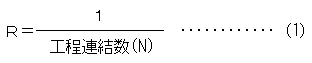 この連結技術もトヨタのDNAのひとつである。 トヨタの連結能力はまさしく装置工業並で、一貫生産ラインをつくり1個流しにするのが得意である。 セルシオは35,000点を1,000ユニット化し、それをSCMで300モジュールにして組立しているので、42H、ハイラックは30,000点を300モジュールにして26H、カローラは22HといわれるからLTは1/50になっているのである。 2.在庫及び中間仕掛品の削減原材料及び仕掛品は0.8日分、LTに換算すると約20H。自動車の部品点数は平均約3万点、100車種としても300万点が管理の対象になる。これを欠品ゼロにすることは不可能に近い。それをゼロにしたのであるから称賛に値する。しかも平均調達時間も0.8×24H=約20Hである。近郊は2Hであるから、かんばんの威力はすごい。これは中国が真似してもできない。過去20年間のトヨタの経営数字を分析すると、原材料0.8日分、中間仕掛り0.8日分、製品0.8日分で、計2.4日分の在庫である。その後、殆ど増減はないことから、トヨタでは「在庫ゼロ」の思想はない。むしろ「必要な在庫は持つ」思想なのである。その必要量が少ないだけなのである。 中間仕掛り品の在庫日数(W、1)×1日の稼働時間(H)代入すると、0.8日分×24H=19.2H 約20H 従って、中間仕掛り品の圧縮によるLT短縮の成果は大きい。 方法としては、
3.生産計画の単位、短縮技術昔は、P、D、C、Aの管理のサークルではないが、本社でたてた、だろう販売の3カ月販売計画(P)が基本だった、今月分は確定、次月は予定、次々月は予測という生産計画の順送りで生産していた。ところが、だろう販売、だろう生産計画の欠点の 第1はあたらないこと、変更率90%以上 第2は後工程の欠品発生にともなう段替えの増加 第3は緊急対策にともなう会議の増加だった。 或る日、後工程(主に組立)から連絡のあった分だけをつくれば、欠品がゼロになるということを発見した。当時のO課長は2.2mmの鉄板に部品名と数量をペンキで書き、From-toという課間の定期部品供給板を発明した。 toの組立より2.2mmの鉄板にペンキをぬった連絡板をもらう。部品供給工程は、その連絡板どおりに物をつくり、現物をつけてFromよりToの組立に運ぶことにした。これで欠品はゼロになった。これがかんばん(当時ペンキで塗ったものはかんばんしかなかったのでかんばんと命名した)のがはじまりである。 次は、3カ月単位の生産計画を月単位、更に週単位に変更した、第1週は確定受注、第2週は予定。第3週は予測というように、準受注生産に切り替えた。 その次は、週を3日間の節に切り替え、実需生産方式になった(N社は最近になって成功したが約30年おくれている)。コンピューターの進化と共に日単位に切り替えた(1990年)。現在は受注の単位を直単位から8Hへ、8Hから4Hへ、そして2Hへ。ただし田原工場の輸出車については3週おくれの準受注生産方式になる。 これは、参考であるが、私が現在(2004年)TPSを指導しているA社は相変わらず、3カ月先のだろう販売、だろう生産、だろう購買、だろう外注なのであるからトヨタの40年前、そっくりであるから、特別不思議がる必要はない。特に昭和28年ころのトヨタは月初めの1日から20日までは、部品をそろえ、21日から30日で自動車を組み立てていたのである(デカンショ生産という)から3カ月区間で進める生産計画はそんなに不思議ではない〔現在のMRPも似たりよったりである〕それを旬、週、節、日、4Hにして、現在は2H単位の生産計画に進化させているから、進化力には驚きである。 トヨタ生産方式とは、かんばんと自動化となっているが、ひとことで言うと、「現状否定のDNA」といえそうである。一見、大野理論と思われやすいが、大野理論を否定した九州工場のレイアウトを見ると「現状否定のDNA」といえそうである。 この優れたトヨタの「現状否定のDNA」を利用して、日本の物造りの改良に役にたてるかが、われわれコンサルタントの使命かも知れない。 4.段取り替え技術昔2000トンプレスは4Hかかっていた。クレーンでの型替えであったので、運搬、位置決めに時間がかかっていたからである。その証拠にR社の段替えは1990年頃でも3Hかゥっていたから、そんなに不思議ではない。現在は5200トンプレスの段取り替えが3分である。通常なら3時間かかるが、わずか3分でできる。3という数字は同じでも、時(H)と分(M)の違いがある。他業界に比し、1/60の圧縮力をもっている。塗装のカラーチェンジは魔術に等しい。 昔、30分、今、1.2秒だからである。しかも組立の機種替えは殆ど自動段替えになっている。 トヨタの1次下請けのダイキャスト工場では450トンの型替えが予熱をふくめ、CT(42S)で出来るという、しかも、試し加工は2個から良品といっているから、正確には2CT(ツーサイクルタイム)の段替えかも知れない。 5.その他の改革技術思いつくままに列挙してみると、次のようになる。
本文は、「進化するトヨタ生産システム」の第1章の一部を掲載したものです。 続きをお読みになりたい方は、「進化するトヨタ生産システム」をお申込み下さい。 |


