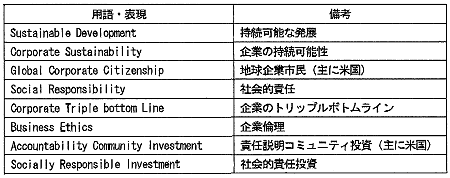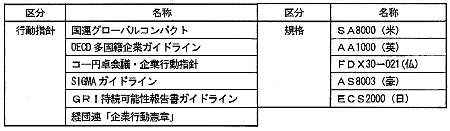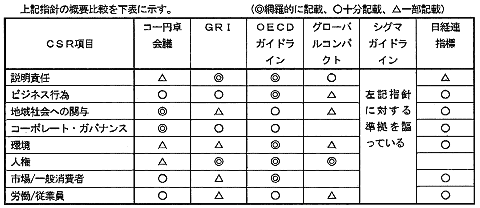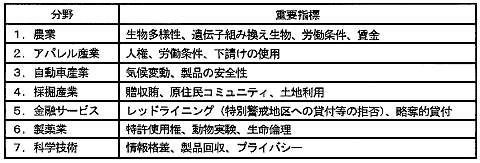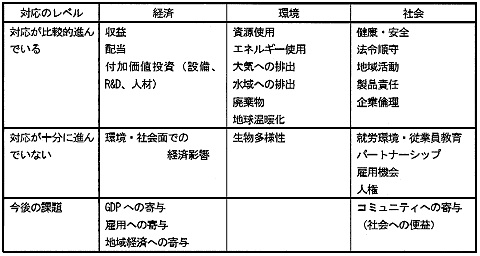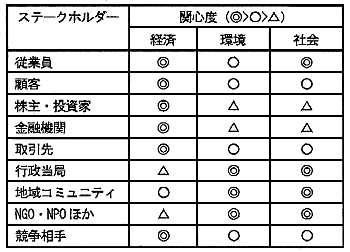| 丂 |
 |
侾丏CSR偲偼壗偐
1.1丂CSR偺掕媊
CSR(Corporate Social Responsibility)偵偼丄偝傑偞傑側夝庍偑偁傝丄崙嵺揑偵崌堄偝傟偨掕媊偼側偄丅偦偺棟桼偼丄婇嬈妶摦傪庢傝姫偔僗僥乕僋儂儖僟乕(棙奞娭學幰丗屭媞丄姅庡丒搳帒壠丄廬嬈堳丄庢堷愭丄抧堟幮夛丄峴惌丄NGO側偳)偺壙抣娤偵婎偯偔婇嬈傊偺娭怱帠偑丄崙傗抧堟丄廆嫵丄廗姷丄抍懱偺栚揑側偳偵傛偭偰堎側傝丄懡條偱丄摿掕偡傞偙偲偑崲擄側偙偲偵傛傞丅
側偍丄堦斒榑偲偟偰丄CSR偺奩摉斖埻偼丄宱嵪丄娐嫬丄幮夛偺僩儕僢僾儖儃僩儉儔僀儞傪峔惉偡傞梫慺偲偟偰懆偊傜傟偰偄傞丅
嶲峫傑偱偵丄CSR偺掕媊偵偮偄偰椺傪偁偘傞丅
- EU儂儚僀僩儁乕僷乕丗CSR偲偼丄乽愑擟偁傞峴摦偑帩懕壜擻側帠嬈偺惉岟偵偮側偑傞偲偄偆擣幆傪婇嬈偑怺傔丄幮夛丒娐嫬栤戣傪帺敪揑偵偦偺帠嬈妶摦媦傃僗僥乕僋儂儖僟乕偲偺憡屳娭學偵庢傝擖傟傞偨傔偺奣擮傪偄偆丅
- BSR(Business for Social Responsibility丗暷崙偺CSR悇恑巗柉抍懱)丗CSR偲偼丄幮夛偑婇嬈偵懳偟偰書偔朄揑丅椣棟揑丄彜嬈揑傕偟偔偼偦偺懠偺婜懸偵徠弨傪崌傢偣丄偡傋偰偺尞偲側傞棙奞娭學幰偺梫媮偵懳偟偰僶儔儞僗傛偔堄巚寛掕傪偡傞偙偲傪堄枴偡傞丅
廬偭偰丄婇嬈偲偟偰偼丄帺屓偺嬈柋丒妶摦斖埻側偳傪峫椂偟偰丄帺幮偵奩摉偡傞CSR傪慖掕偟偰丄懳張偡傞偙偲偑昁梫偲側傞丅
乮嶲峫乯CSR偺奣擮丒昞尰
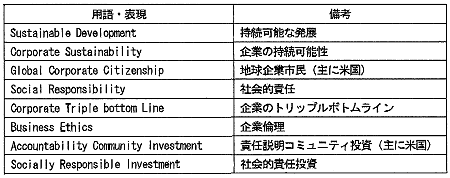
1.2丂CSR偺曕傒
CSR妶摦偼丄寛偟偰怴偟偄傕偺偱偼側偄丅
暷崙偱偼丄傾儖僐乕儖傗僞僶僐婇嬈傊偺搳帒傪旔偗傛偆偲偡傞嫵夛傗廆嫵抍懱偺怣嬄偵婎偯偔摦偒偑丄1920擭戙偵巒傑偭偨丅
偙傟偑60擭戙屻敿偐傜70擭戙慜敿偺儀僩僫儉斀愴塣摦傗徚旓幰塣摦丄70乣80擭戙偺斀傾僷儖僩僿僀僩塣摦偺崅傑傝側偳傪宊婡偵丄暫婍丄僞僶僐丄傾儖僐乕儖丄僊儍儞僽儖丄摦暔幚尡側偳偵娭傢傞斀幮夛揑嬈庬傪夞旔偡傞僱僈僥傿僽丒僗僋儕乕僯儞僌偵傛傞SRI(Social Responsibility Investment)偲偟偰惃椡傪奼戝偟偰偒偨丅
俀丏偄傑丄側偤CSR偐
2.1丂崙嵺揑側CSR偺攇
嬤擭丄CSR偑惡崅偵媮傔傜傟傞傛偆偵側偭偨攚宨偲偟偰偼丄埲壓偺梫場偑偁偘傜傟傞丅
乮1乯婇嬈妶摦椞堟偺奼戝
嵟戝偺梫場偲偟偰婇嬈妶摦偺婯柾偺奼戝丒暋嶨壔偑嫇偘傜傟傞丅偙偺寢壥丄幮夛偺嬿乆偵傑偱婇嬈妶摦偺僀儞僷僋僩偑柍帇偱偒側偄戝偒偝偱媦傃傛偆偵側偭偨丅
懡崙愋婇嬈偵戙昞偝傟傞傛偆偵婇嬈妶摦偑僌儘乕僶儖壔偡傞偲丄恑弌愭偺崙偺宱嵪丄娐嫬丄屬梡丄偝傜偵偼崙壠庡尃偵傑偱塭嬁傪梌偊傞丅敪揥搑忋崙偵偍偗傞晄姰慡側朄婯惂偺壓偱偼丄帣摱楯摥丒嶏庢楯摥丄娐嫬攋夡側偳偑敪惗偟傗偡偄丅
乮2乯IT壔偺恑揥
IT媄弍偺恑曕偼丄忣曬偺悽奅揑側弖帪揥奐傪壜擻偵偟丄婇嬈妶摦偺僌儘乕僶儖丒儗儀儖偱偺娔帇傪壜擻偵偟偨丒傑偨丄僀儞僞乕僱僢僩偵傛偭偰嫟捠偺壽戣偵娭怱傪帩偮NGO丄屄恖傪栤傢偢丄僗僥乕僋儂儖僟乕偑僱僢僩儚乕僋壔偝傟丄婇嬈昡壙忣曬偑娭學幰偺娫偱嫟桳偝傟傞偙偲偵側偭偨丅
偙傟偼丄栤戣傪堷偒婲偙偡偲丄悽奅揑側婯柾偱偺嫮椡側僀儞僷僋僩傪旐傝偐偹側偄偙偲傪堄枴偡傞丅
乮3乯NPO丒NGO偵傛傞斀幮夛揑峴堊偺捛媦
- 僟僂丒働儈僇儖偵懳偡傞僫僷乕儉抏惢憿拞巭梫媮(1969擭)丗儀僩僫儉愴憟
- GM偵懳偡傞撿傾偐傜偺揚戅梫媮(1971擭)丗恖庬妘棧惌嶔
- 僴乕僶乕僪戝妛偵懳偡傞僈儖僼愇桘姅攧媝梫媮丗崟恖嵎暿
- 暷娐嫬NGO丒CERES偑丄僶儖僨傿乕僘崋帠審(1989擭)傪庴偗偰乽僶儖僥傿乕僘偺朄懃乿傪敪昞
- 僔僃儖偺愇桘孈嶍僾儔僢僩儂乕儉奀梞搳婞偵娭偡傞峈媍塣摦
- 僫僀僉惢昳晄攦塣摦丗儀僩僫儉偵偍偗傞帣摱楯摥
- 暷崙偺堚揱巕慻傒姺偊怘昳偺墷廈巗応偐傜偺掲傔弌偟
- 暷儘儞儘儞丄儚乕儖僪僐儉偺晄惓宱棟僗僉儍儞僟儖捛媮
尰嵼捛媮偝傟丄忣曬岞奐偑尩偟偔媮傔傜傟偰偄傞帠椺
- 僞僶僐夛幮丗働僯傾偵偍偄偰丄僞僶僐擾壠偵傛傞曐岇嬶側偟偱偺嶦拵嵻嶶晍嶌嬈傪曻抲偟偰偄傞丅
- 愇桘夛幮丗僫僀僕僃儕傾偵偍偄偰丄僷僀僾儔僀儞偺桘楻傟傪曻抲偟偰偄傞丅
- 惔椓堸椏悈夛幮丗恑弌愭偺撿僀儞僪偺懞偱堜屗悈屚傟偑敪惗丄婇嬈偼塉晄懌傪庡挘丅
乮4乯NGO偵傛傞僌儕乕儞丒僐儞僔儏乕儅儕僘儉
NGO偑丄撈帺偺婎弨偱婇嬈傪昡壙偟丄忣曬傪徚旓幰偵棳偟偰丄偦偺婇嬈偺惢昳偺晄攦枖偼峸擖傪悇彠偡傞妶摦偑戝偒側塭嬁椡傪帩偮偵帄偭偰偄傞丅
- CEP(Council on Economic Priorities)
NGO慻怐偲偟偰69擭偵僯儏乕儓乕僋偱愝棫偝傟偨丅偦偺妶摦偼幮夛娐嫬揑娤揰偐傜婇嬈傪昡壙偟丄係抜奒偵奿晅偗偟偰丄徚旓幰側偳偵偦偺忣曬傪採嫙偡傞傕偺偱偁傞丅
偦偙偱偺昡壙偼丄師偺俈崁栚偐傜側傞丅
仭娐嫬丄仭彈惈偺搊梡丄仭儅僀僲儕僥傿偺搊梡丄仭婑晅丄仭楯摥娐嫬丄仭壠懓偺暉棙丄仭忣曬奐帵
- Co-op America
82擭偵儚僔儞僩儞D.C.偱愝棫偝傟偨NGO偱丄僂僄僽僒僀僩偱丄徚旓嵿惗嶻夛幮栺350幮偺忣曬傪採嫙偟偰偄傞丅偦偙偱偼丄師偺忣曬偑丄徻偟偔採嫙偝傟傞丅
仭婇嬈奿晅偗昡壙丄仭幮夛丒娐嫬娭楢帠崁偱偺婇嬈偺徿敱棜楌丄仭僌儖乕僾婇嬈丄仭僽儔儞僪側偳
乮5乯SRI乮Socially Responsible Investment乯偺惃椡奼戝
SRI搳帒妶摦偼丄師偺俁庬椶偵暘偗傜傟丄偦偙偱偼丄擭嬥婎嬥偺摦偒偑摿偵栚棫偮丅
侾乯僗僋儕乕僯儞僌(CSR傪峫椂偡傞搳帒怣戸丒擭嬥塣梡丗億僕僥傿僽乛僱僈僥傿僽僗 僋儕乕僯儞僌乯
- 2003擭偵偍偗傞暷崙SRI巗応偺搳帒塣梡帒嶻巆崅偼俀挍1750壄僪儖(栺240挍墌)丄偙偺偆偪僗僋儕乕儞塣梡偼慡懱偺99亾偺俀挍1540壄僪儖傪愯傔傞丅偙傟偼憤塣梡帒嶻偵懳偟偰11亾傪愯傔傞丅1995擭偺SRI塣梡帒嶻巆崅偑6,390壄僪儖偱偁偭偨偙偲偐傜丄偦偺怢傃偼嬃偔傎偳媫寖偱偁傞丅
- 墷廈偱偺2003擭偺SRI巗応偼3,482壄儐乕儘(45.5挍墌)掱搙偲悇掕偝傟傞丅偙偺偆偪丄僆儔儞僟偑1,814壄儐乕儘丄塸崙偑1,478壄儐乕儘偱偁傞丅
- 擔杮偱杮奿揑側SRI塣梡偑巒傑偭偨偺偼1999擭偱丄20004擭俁寧枛偺憤妟偼1,027壄墌偵夁偓側偄丅
俀乯姅庡媍寛尃偺峴巊乮幮夛揑壽戣偵娭偡傞姅庡採埬乛媍寛尃峴巊丄僄儞僎乕僕儊儞 僩乯
暷崙偺婡娭搳帒壠丒擭嬥婎嬥偺俀幮偺椺傪嫇偘傞丅
- 僇儕僼僅儖僯傾廈岞柋堳戅怑擭嬥婎嬥(Cal PERS)
媍寛尃峴巊偺婎弨傪掕傔丄搳帒愭婇嬈偵愑擟偁傞峴摦傪傕偲傔偰姅庡峴摦傪峴偆丅
嬶懱揑偵偼搳帒愭偵師偺峴摦傪傕偲傔傞丅
仭朄椷弲庣丄仭僌儘乕僶儖丒僒儕僶儞尨懃(恖尃曐岇丄嫮惂楯摥丄嵎暿嬛巭側偳)媦傃儅僋僽儔僀僪尨懃(楯摥幰偺尃棙側偳)偺弲庣丄仭恖尃怤奞偺攔彍丄仭廬嬈堳偲壠懓偺懜尩偲岾暉
- TIFF-CREF
乽挿婜揑側姅庡壙抣偺岦忋偼丄搳帒愭婇嬈偺庢掲栶夛偑幮夛揑愑擟偲岞嫟偺棙塿傪怲廳偵峫椂偡傞偙偲偲堦抳偡傞乿偲偺婎杮揑側峫偊曽傪懪偪弌偟丄婇嬈偵師偺曽恓偺妋棫偲幚慔偲傪媮傔傞丅
仭婇嬈偺憖嬈媦傃惢昳偺娐嫬傊偺僀儞僷僋僩丄仭偡傋偰偺恖岥僙僌儊儞僩偺屬梡婡夛偺暯摍仭廬嬈堳嫵堢偲擻椡奐敪丄仭抧堟幮夛偺岞嫟偺棙塿偵僱僈僥傿僽側塭嬁傪梌偊傞婇嬈峴摦偺昡壙
俁乯僐儈儏僯僥傿搳帒乮峳攑偟偨抧堟傊嵞奐敪帒嬥偺採嫙乯
2.2丂壛懍偝傟傞CSR
悽奅奺崙偱偺庢傝慻傒偑塿乆壛懍偝傟傞偙偲偑梊憐偝傟丄堦帪揑側僽乕儉偱廔傢傞傕偺偱偼側偄丅
- 僄價傾儞僒儈僢僩愰尵
CSR(婇嬈偺幮夛揑愑擟)偼丄2003擭俇寧偵奐嵜偝傟偨庡梫崙庱擼夛媍(僄價傾儞丒僒儈僢僩)偵偍偗傞俧俉愰尵偵傕庢傝擖傟傜傟偨丅
- 媫憹偡傞CSR偺巜恓丒婯奿
抍懱丒崙壠偵傛傞CSR峴摦巜恓丒婯奿偺悢偼丄婛偵悢廫審傪悢偊傞偲偄傢傟傞丅庡梫側傕偺傪壓昞偵帵偡丅
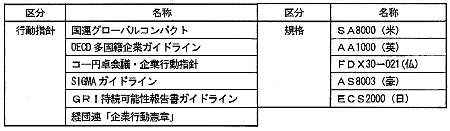
- ISO乮崙嵺昗弨壔婡峔乯偵偍偗傞CSR婯奿壔偺寛掕
ISO偼丄棟帠夛偵偍偄偰CSR偺崙嵺婯奿壔偺挷嵏傪嵦戰(2001擭係寧)偟丄2001擭俆寧偐傜COPOLCO(徚旓幰惌嶔埾堳夛)偵傛偭偰崙嵺婯惂壔偺挷嵏傪奐巒偟偨丅
偦偺挷嵏寢壥偼丄崙嵺婯奿壔傪採埬偡傞傕偺偵偰丄乽婇嬈偺幮夛揑愑擟偵娭偡傞ISO婯奿偺僨僓僀儞傾價儕僥傿媦傃僼傿乕僕價儕僥傿曬崘彂乿偲偟偰採弌偝傟偨(2002擭俆寧)丅
偙傟偵懳偟ISO棟帠夛偼丄峏側傞専摙偑昁梫偲偟偰丄TMB偺壓偵CSR崅摍帎栤埾堳挿傪愝抲(2002擭俋寧)偟丄崙嵺婯奿壔偺懨摉惈偵偮偄偰媍榑傪恑傔丄嵟廔姪崘傪採弌偟偨(2004擭係寧)丅
侾乯嵟廔姪崘
- 庡側撪梕
- ISO偼SR偺昗弨壔傪悇恑偡傞偨傔偺慜採忦審(ILO偲偺楢実丄懠偺僈僀僟儞僗偲偺憡堘偺尒嬌傔側偳)傪採帵
- 揔崌惈昡壙偵棙梡偝傟側偄僈僀僟儞僗丒僪僉儏儊儞僩偺嶌惉
- 搑忋崙偺嶲壛嫮壔傪悇彠
- 愭恑崙偲敪揥搑忋崙偺Twinning宍幃偱偺儕乕僟乕僔僢僾億僗僩傪愝偗傞偙偲傪姪崘
- 婛懚偺媄弍埾堳夛偱偼側偔怴偨側埾堳夛偺愝抲傪悇彠
- 昗弨壔偺媍榑偵偼棙奞娭學幰偺嶲壛傪梫惪
- 僈僀僟儞僗丒僪僉儏儊儞僩偺梫審
- 嶻嬈奅偽偐傝偱偼側偔丄懠偺慻怐偱傕棙梡偱偒傞丅
- 寢壥丄幚峴偵傛傞夵慞傪嫮挷偡傞丅
- 嫟捠偺梡岅傪庴偗擖傟偰偄傞丅
- 偝傑偞傑側暥壔丄幮夛丄娐嫬偺SR(CSR偺怴偟偄柤徧)偵懳墳偱偒傞丅
- 婛懚偺SR婯惂傪曗姰偱偒傞丅
- 惌晎偑壥偨偡傋偒栶妱傪庛傔傞傕偺偱偼側偄丅
- 慻怐偺婯柾傪栤傢偢桳梡偱偁傞丅
- SR偺塣塩丄棙奞娭學幰偺摿掕丄怣棅惈偺妋曐偵娭傢傞庤抜傪採嫙偡傞丅
- 柧妋側暥復昞尰偵傛傞傕偺偱偁傞丅
俀乯TMB偺寛掕
TMB偼丄偙偺姪崘傪庴偗偰2004擭俇寧丄師偺傛偆側寛掕傪壓偟偨丅
- TMB偵捈懏偡傞WG傪愝抲偟偰丄姪崘傪慜採忦審丒峔惉梫慺偲偡傞怴嶌嬈偵拝庤偡傞丅
- 埲壓偵偮偄偰恑傔丄2004擭俋寧偺TMB夛媍偵採弌偡傞丅
- WG偼Twinning宍幃偲偟丄2004擭俉寧15擔傑偱偵姴帠崙岓曗偺採弌傪媮傔傞丅
- 僞僗僋僼僅乕僗傪愝偗偰WG偺嶌嬈崁栚偵偮偄偰偺採埬傪嶌惉偡傞丅
廬偭偰丄偙偺傑傑弴挷偵恑傔偽丄2005擭弶偵WG偼妶摦傪奐巒丄俀擭屻偵偼曬崘彂偺姰
惉偑婜懸偝傟傞丅
2.3丂奺崙偺摦偒
乮1乯暷崙
暷崙偱偺CSR傊偺庢傝慻傒偺摿挜偼丄僐乕億儗乕僩僈僶僫儞僗丄婇嬈椣棟丄僐儞僾儔僀傾儞僗傪儀乕僗偵丄愊嬌揑側宱嵪壙抣偺捛媮傪捠偠偰幮夛偵億僕僥傿僽側塭嬁傪傕偨傜偡妶摦傪揥奐偟偰偄傞丅
- 婇嬈妶摦偑庡懱偲側傞丅偦偺庢傝慻傒傕朄椷弲庣傪挻偊偰幮夛傪棙偡傞偲偄偆丄抧堟僐儈僯儏僥傿偱偺婇嬈巗柉妶摦(Corporate Citizenship)偑拞怱偱偁傞丅
傑偨丄桪愭暘栰傪寛傔丄乽愴棯揑廤拞乿偵傛偭偰屄惈傪弌偡偙偲傪怱偑偗偰偄傞丅
- 僄儞儘儞丄儚乕儖僪僐儉偺暡忺寛嶼傪宊婡偵丄僒乕儀僀儞僘丒僆僋僗儗乕朄(婇嬈
夵妚朄)偑惉棫偟丄娔嵏丒撪晹娗棟懱惂偺嫮壔偵娭偡傞婯掕偑惙傝崬傑傟偨丅
乮2乯塸崙
塸崙傪偼偠傔墷廈奺崙偱偼丄CSR傗SRI傪懁柺巟墖偡傞朄棩惂掕偺摦偒偑栚棫偮丅
- 2000擭俈寧偵擭嬥朄偑夵惓偝傟丄擭嬥塣梡庴戸幰(婡娭搳帒壠)偼丄帺屓偺搳帒尨懃傪婰嵹偡傞拞偱丄埲壓偺奐帵偑媊柋晅偗傜傟偨丅
- 搳帒柫暱偺慖掕丒曐桳丒攧媝偵偍偄偰丄幮夛丄娐嫬傑偨偼椣棟柺傪峫椂偟偨斖埻
- 媍寛尃峴巊傪娷傓搳帒偵敽偆尃棙峴巊偺婎杮揑曽恓
- 尰嵼専摙拞偺夛幮朄夵惓偵偰傕丄戝婇嬈偵偍偄偰偼丄偦偺擭師曬崘偵偍偗傞宱塩幰偺愢柧偺拞偱乽娐嫬丄僐儈儏僯僥傿丄幮夛丄椣棟丄朄椷弲庣偵娭偡傞曽恓偲僷僼僅乕儅儞僗乿偵娭偡傞廳梫忣曬偺柧帵偑媊柋晅偗傜傟偰偄傞丅
- 2001擭係寧偵偼CSR扴摉戝恇偑擟柦偝傟偨丅
乮3乯僼儔儞僗
- 2001擭俆寧偵偼丄SRI偺晛媦偵偮側偑傞CSR娭楢偺忣曬奐帵傪掕傔偨夛幮朄摍偺戝暆側夵惓偑峴傢傟偨丅偦偙偱偼丄擭嬥婎嬥傗廬嬈堳挋拁傪塣梡偡傞搳帒僼傽儞僪偑丄忋応婇嬈偵懳偟偰婇嬈妶摦偺幮夛揑丒娐嫬揑塭嬁偵娭偡傞曬崘彂偺嶌惉丄奐帵傪媊柋晅偗偰偄傞丅
- 2002擭俆寧偵偼丄塸崙偵師偄偱CSR扴摉戝恇偑擟柦偝傟偨丅
乮4乯僪僀僣
2001擭俉寧傛傝擭嬥婎嬥塣梡夛幮偵懳偟偰丄婎嬥偺塣梡偵偁偨偭偰椣棟柺丄娐嫬柺丄幮夛柺傊偺攝椂偵偮偄偰曬崘偡傞偙偲偑媊柋晅偗傜傟偨丅
乮5乯EU
CSR傪婇嬈偵媮傔偰丄EU撪偱偺崙丒抧堟偵傛傞搳帒偺曃傝偵傛傞幐嬈幰敪惗傪杊偖傋偔丄峴惌偑屻墴偟傪偟偰偄傞偺偑摿挜偱偁傞丅
- 2001擭俈寧墷廈埾堳夛偼僌儕乕儞儁乕僷乕366乽CSR偺偨傔偺墷廈偺榞慻傒偺懀恑乿傪採弌偟偨丅偦偙偱偼丄CSR懀恑偺偨傔偺愴棯偺榞慻傒傪採帵偟丄CSR偺媍榑傪姭婲偟偰偄傞丅偦偺忋偱丄2003擭傑偱偵愝棫梊掕偺墷廈姅幃巗応偵偍偄偰幮夛揑愑擟搳帒僼傽儞僪愝棫偺婎慴偲側傞娐嫬丒幮夛僷僼僅乕儅儞僗偵桪傟偨婇嬈偐傜側傞墷廈姅壙巜昗偺昁梫惈傪鎼偭偰偄傞丅
- 2002擭俈寧丄摨埾堳夛偼儂儚僀僩儁乕僷乕乽CSR丗帩懕壜擻側婇嬈偺峷專乿傪採弌偟丄EU惌嶔偺偁傜備傞懁柺偱CSR偵庢傝慻傫偱偄偔偙偲傪昞柧偟偨丅摿偵丄峴摦婯斖丄宱塩婯弨丄夛寁丄僜乕僔儍儖丒儔儀儕儞僌丄愑擟偁傞搳帒偵廳揰傪抲偄偰偄傞丅
- 2002擭10寧丄CSR儅儖僠僗僥乕僋儂儖僟乕僼僅乕儔儉(CSR EMS Forum)傪敪懌偝偣丄婇嬈丄楯摥慻崌丄NGO丄搳帒壠丄徚旓幰側偳偑嶲壛偟偰丄婇嬈偺幮夛揑愑擟偵偮偄偰墷廈慡懱偺僐儞僙儞僒僗傪宍惉偡傞懱惂傪嶌偭偨丅
- EU挷払巜椷(2003擭擭枛)偵傛傝EU偺娐嫬丒幮夛丒宱嵪娭楢巜椷傪婯惂偟弴庣偟側偄抍懱偼丄擖嶥僾儘僙僗偐傜彍奜偝傟傞丅
乮6乯擔杮
傢偑崙偱偼丄宱嵪嶻嬈徣偑ISO丒CSR娭楢埾堳夛偵埾堳傪憲傞偲偲傕偵丄傢偑崙偺庡挘傪婯奿偵斀塮偝偣丄婯奿壔屻偺摫擖懳墳婡娭偲偟偰偺栶妱傪晧偆CSR昗弨埾堳夛(帠柋嬊擔杮婯奿嫤夛)傪敪懌偝偣偨丅
扐偟丄嶻嬈奅偑CSR婯奿壔偺摦偒偵懳偟偰斀懳偺巔惃傪偲傝懕偗偰偄傞偙偲傕偁偭偰丄嬶懱揑側妶摦偼尒偊側偐偭偨丅
偟偐傞偵丄ISO偺婯奿壔寛掕傪庴偗偰丄嶻嬈奅傕婯奿壔偵嫤椡偡傞巔惃傪懪偪弌偟偰偄傞丅
偙偺懠丄CSR偵娭偡傞崙撪揑側摦偒偵偼丄埲壓偑偁傞丅
- 宱抍楢嶱壓偺奀奜帠嬈妶摦娭楢嫤媍夛偑丄崙撪偺CSR偺摦偒傪惛椡揑偵挷嵏偟偰丄忣曬偺採嫙傪峴偭偰偄傞丅
- 宱嵪摨桭夛偑丄戞15夞婇嬈敀彂(2003擭俁寧)偵偰幮夛揑愑擟宱塩偺巜昗傪採帵偟丄偐偮丄婇嬈偵傾儞働乕僩偲偟偰夞摎傪媮傔丄CSR宱塩庢傝慻傒忬嫷傪暘愅丒敪昞偟偰偄傞丅
- 宱嵪抍懱楢崌夛偑丄CSR傪堄幆偟偰婇嬈峴摦寷復傪夵掕偟偨(2004擭俆寧)丅
- 婇嬈偺愑擟偁傞峴摦傪懄偡朄惂搙夵妚傕恑傔傜傟偰偄傞丅乽岞塿捠曬幰曐岇惂搙乿乽徚旓幰抍懱慽徸惂搙乿丄宱嵪嶻嬈徣偵傛傞乽撪晹摑惂僈僀僪儔僀儞乿嶔掕丄乽彜朄夵惓乿偵傛傞宱塩偺娔帇丒幏峴惂搙偺夵掕
- 搶嫗徹寯庢堷強偺乽摑帯尨懃乿偺嶔掕偵傛傝乽桳壙徹寯撏弌彂乿乽桳壙徹寯曬崘彂乿偵偍偄偰偼丄僐乕億儗乕僩丒僈僶僫儞僗忣曬丄儕僗僋忣曬丄宱塩幰偵傛傞嵿柋丒宱塩惉愌偺暘愅偵娭偡傞忣曬奐帵偺廩幚偑媮傔傜傟偰偄傞丅
俁丏CSR偑梫媮偡傞傕偺
崙嵺揑偵崌堄偝傟偨CS巜昗偼側偄傕偺偺丄岞奐偝傟偰偄傞巜恓丒婯奿偺撪梕偐傜丄偦偺奣梫傪攃埇偡傞偙偲偑偱偒傞丅
3.1丂婇嬈峴摦巜恓
乮1乯崙楢僌儘乕僶儖僐儞僷僋僩乮The Global Compact乯
99擭侾寧偺乽悽奅宱嵪僼僅乕儔儉(僟儃僗夛媍)乿偵偍偄偰崙楢偺傾僫儞帠柋憤挿偵傛傝採彞偝傟偨婇嬈偺峴摦婯斖偱丄乽恖尃乿乽楯摥乿乽娐嫬乿偺俁崁栚偵娭偡傞俋尨懃偐傜側傞丅
僌儘乕僶儖僐儞僷僋僩偼丄ILO(崙嵺楯摥婡娭)偺巊柦乽楯摥偺婎杮尨懃媦傃尃棙偵娭偡傞ILO愰尵乿傪悽奅揑偵峀傔傞偨傔偺廳梫側庤抜偱傕偁傞丅
- 恖尃
- 崙嵺揑偵愰尵偝傟偰偄傞恖尃偺曐岇傪巟帩偟丄懜廳偡傞
- 恖尃怤奞偵壛扴偟側偄
- 楯摥
- 慻崌寢惉偺帺桼偲抍懱岎徛尃傪幚峴偁傞傕偺偵偡傞丅
- 偁傜備傞庬椶偺嫮惂楯摥傪攔彍偡傞丅
- 帣摱楯摥傪幚岠揑偵攑巭偡傞丅
- 屬梡偲怑嬈偵娭偡傞嵎暿傪攔彍偡傞B
- 娐嫬
- 娐嫬栤戣偺梊杊揑側傾僾儘乕僠傪巟帩偡傞丅
- 娐嫬偵懳偟偰堦憌偺愑擟傪晧偆偨傔偺僀僯僔傾僥傿僽傪偲傞丅
- 娐嫬傪庣傞偨傔偺媄弍偺奐敪偲晛媦傪懀恑偡傞丅
乮2乯OECD懡崙愋婇嬈僈僀僪儔僀儞
OECD壛柨崙惌晎偑懡崙愋婇嬈偵懳偟嫤摨偟偰峴偆姪崘偱偁傞丅
婇嬈偑弲庣偡傋偒堦斒尨懃偲偟偰乽恑弌愭偺帩懕揑壜擻側奐敪偺払惉偵攝椂偟丄幮
夛丄娐嫬丄宱嵪敪揥偵峷專偡傋偒偙偲乿偑嫇偘傜傟丄師偵娭傢傞徻嵶側峴摦婎弨偑婯
掕偝傟偰偄傞丅
(1)忣曬奐帵丄(2)屬梡媦傃楯摥娭學丄(3)娐嫬丄(4)憽榙偺杊巭丄(5)徚旓幰棙塿丄(6)壢妛媄弍(媄弍堏揮側偳)丄(7)嫞憟(斀嫞憟揑庢傝寛傔偺嬛巭側偳)丄(8)惻(擺惻媊柋偺棜峴)側偍丄嵦戰崙撪偱僈僀僪儔僀儞堘斀偺楯摥憟媍偑敪惗偟偨応崌偵偼NCP(擔杮偱偼奜柋徣丄岤惗楯摥徣丄宱嵪嶻嬈徣偑奩摉偡傞)偵採慽偱偒傞丅
乮3乯僐乕墌戩夛媍丒婇嬈偺峴摦巜恓
僐乕墌戩夛媍偼丄86擭偵僗僀僗偺僐乕(Caux)偵偍偄偰愝棫偝傟偨擔暷墷偺婇嬈宱塩幰偺抍懱偱偁傞丅愝棫摉弶偼丄捠彜栤戣傪庡梫媍戣偲偟偰偄偨偑丄乽嫟惗乿乽岞惓乿乽恖娫偺懜尩乿偺棟擮偑採彞偝傟丄悽奅偺暯榓偲埨掕偵懳偡傞幮夛揑丒宱嵪揑嫼埿偺尭彮偵岦偗偰壥偨偡傋偒僌儘乕僶儖婇嬈偺愑擟偵偮偄偰摙媍傪峴偄丄94擭偵偦偺寢壥傪乽婇嬈偺峴摦巜恓乿偵傑偲傔偨丅
- 堦斒尨懃
- 婇嬈偺愑擟丗姅庡偺傒側傜偢僗僥乕僋儂儖僟乕偺慡偰傪懳徾偵偡傞
- 婇嬈偺宱嵪揑幮夛揑塭嬁丗僀僲儀乕僔儑儞丄惓媊丄抧媴僐儈儏僯僥傿傪栚巜偡
- 婇嬈偺峴摦丗朄棩偺暥尵埲忋偵怣棅偺惛恄傪廳帇偡傞
- 儖乕儖偺懜廳
- 懡妏揑杅堈偺巟帩
- 娐嫬傊偺攝椂
- 堘朄峴堊偺杊巭
- (埲壓偺)僗僥乕僋儂儖僟乕偵婇嬈偑壥偨偡傋偒愑擟
- 屭媞
- 廬嬈堳
- 僆乕僫乕丒搳帒壠
- 巇擖愭
- 嫞憟憡庤
- 抧堟幮夛
乮4乯SIGMA僈僀僪儔僀儞
塸崙杅堈嶻嬈徣偺巟墖傪庴偗偰丄乽塸崙婯奿嫤夛乿丄乽傾僇僂儞僞價儕僥傿乿丄乽僼僅乕儔儉丒僼僅乕丒僓丒僼儏乕僠儍乕乿偺俁慻怐偑庡摫偟偰丄僒僗僥傿僫價儕僥傿丒儅僱僕儊儞僩傪幚慔偡傞偨傔偺僈僀僪儔僀儞偲偟偰1997擭俈寧偵棫偪忋偘偨傕偺偱偁傞丅
- 俆偮偺帒杮丗
- 帺慠帒杮(娐嫬)
- 幮夛帒杮(幮夛偲偺娭學偲幮夛峔憿)
- 恖揑帒杮(恖乆)
- 惢憿帒杮(屌掕帒嶻)
- 嬥梈帒杮(懝塿丄攧傝忋偘丄姅幃丄尰嬥側偳)偺堐帩丒嫮壔偲愢柧愑擟傪壥偨偡偨傔偵丄
- PDCA儌僨儖偵婎偯偔係僼僃乕僘丗
- 儕乕僟乕僔僢僾偲價僕儑儞
- 寁夋
- 幚巤
- 娔帇丄尒捈偟丄曬崘
偐傜峔惉偝傟偰偄傞丅
傑偨丄帩懕壜擻側敪揥偵娭楢偡傞20偺婯奿偲僈僀僪儔僀儞偲傪巊梡偱偒傞傛偆偵傑偲傔偰偄傞丅
乮5乯GRI乮Global Reporting Initiative乯僒僗僥僫價儕僥傿丒儕億乕僥傿儞僌丒僈僀僪儔僀儞
暷崙偺娐嫬NGO偱偁傞CERES(Goalition for Environmentaliy Responsible Economies)偼丄97擭偵崙楢娐嫬寁夋(UNEP)偲嫟摨偱GRI傪敪懌偝偣偨丅
GRI偼丄婇嬈丄NGO丄夛寁巑抍懱丄楯摥抍懱丄娐嫬曐岇抍懱丄婡娭搳帒壠偐傜偺嶲壛幰偱峔惉偝傟傞儅儖僠丒僗僥乕僋儂儖僟乕廤抍偱偁傝丄懡柺揑側堄尒傪斀塮偝偣偰忣曬奐帵偺僼僅乕儅僢僩乽帩懕壜擻惈曬崘彂乿傪嶌惉偡傞偲偄偆庢傝慻傒傪恑傔偰偄傞丅
GRI僈僀僪儔僀儞偼丄宱嵪丒娐嫬丅幮夛偺俀俁梫慺(triple bottom line)偵娭偡傞婇嬈偺僷僼僅乕儅儞僗傪曬崘偡傞榞慻傒傪採帵偡傞傕偺偱偁傞偑丄偦偙偱庢傝忋偘傜傟偰偄傞僷僼僅乕儅儞僗巜昗偵偼丄廫暘偵拲堄傪暐偆昁梫偑偁傞丅
僷僼僅乕儅儞僗巜昗偵偼丄師偺崁栚偑娷傑傟傞丅
- 宱嵪
捈愙揑塭嬁(屭媞丄嫙媼嬈幰丄廬嬈堳丄搳帒壠丄岞嫟晹栧)娫愙揑塭嬁
- 娐嫬
尨嵽椏丄僄僱儖僊乕丄悈丄惗暔懡條惈丄攔弌暔丒曻弌暔丒攑婞暔丄嫙媼嬈幰丄惢昳偲僒乕價僗丄朄椷弲庣丄桝憲丄偦偺懠慡斒
- 幮夛
楯摥姷峴偲岞惓側楯摥忦審(屬梡丄楯摥幰偲宱塩幰偺娭學丄寬峃偲埨慡丄嫵堢孭楙傎偐)
恖尃(愴棯丒儅僱僕儊儞僩丄旕嵎暿丄寢幮偺帺桼丒抍懱岎徛丄帣摱楯摥丄嫮惂楯摥傎偐)幮夛(抧堟幮夛丄憽榙丒墭怑丄惌帯專嬥丄嫞憟丒壙奿愝掕)惢憿暔愑擟(徚旓幰偺寬峃偲埨慡丄惢昳丒僒乕價僗丄峀崘丄僾儔僀僶僔乕曐岇)
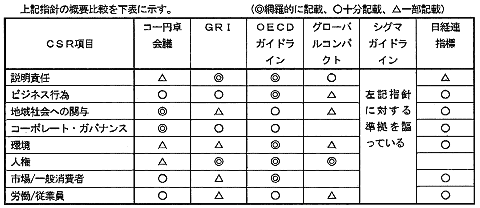
3.2丂抍懱丒崙壠愴棯
乮1乯SA8000乮Social Accountability 8000乯
暷崙偺CSR昡壙婡娭CEP(Council for Economic priorities)偑曣懱偲側偭偰97擭偵愝棫偟偨抍懱CEPAA(Council on Economic Priorities on Accreditation Agency)偵傛偭偰婯掕偝傟偨乽帣摱楯摥丒嫮惂楯摥丒嶏庢楯摥栤戣偵娭偡傞擣徹婯奿乿偱偁傞丅
摉婯奿偼丄弲庣偡傋偒婯掕偺傒側傜偢丄戞嶰幰擣徹偺巇慻傒傪旛偊偰偄傞丅
傢偑崙偱偼丄SGS僌儖乕僾傎偐俋幮偑偙偺擣徹婡娭偲側偭偰偄傞丅
婯掕偼丄埲壓偺俋崁栚傛傝側傞丅
(1)帣摱楯摥丄(2)嫮惂楯摥丄(3)寬峃偲埨慡丄(4)寢幮偺帺桼偲抍懱岎徛尃丄(5)嵎暿(恖庬丄惈側偳)丄(6)挦敱(懱敱丄埿埑側偳)丄(7)楯摥帪娫丄(8)曬廣丄(9)儅僱僕儊儞僩僔僗僥儉(暥彂偵傛傞奐帵)
乮2乯AA1000
塸崙偺幮夛椣棟愢柧愑擟尋媶強(Institute of Social and Ethcal Accountability)偑奐敪偟偨AA1000僔儕乕僘偼丄婇嬈偑幮夛椣棟偵娭偡傞曬崘傪峴偆嵺丄偳偺傛偆側僾儘僙僗傪摜傓昁梫偑偁傞偐饚儝偡丄僾儘僙僗偵娭偡傞婯奿偱偁傞丅
僷僼僅乕儅儞僗偺悈弨偵偮偄偰偼婯掕偟偰偄側偄丅
偦偺峔惉偼丄係偮偺崁棫偰偲12偺僾儘僙僗偲偐傜側傞丅
- 寁夋丗
丂丂丂僾儘僙僗侾丂僐儈僢僩儊儞僩偲摑帯庤懕偒傪妋棫偡傞丅
丂丂丂僾儘僙僗俀丂僗僥乕僋儂儖僟乕傪妋掕偡傞
丂丂丂僾儘僙僗俁丂壙抣傪婯掕丒尒捈偡
- 夛寁丗僾儘僙僗係丂壽戣傪妋掕偡傞
丂丂丂僾儘僙僗俆丂僾儘僙僗偺斖埻傪寛掕偡傞
丂丂丂僾儘僙僗俇丂巜昗傪妋掕偡傞
丂丂丂僾儘僙僗俈丂忣曬傪廂廤偡傞
丂丂丂僾儘僙僗俉丂忣曬傪暘愅偟丄栚揑傪愝掕偟丄夵慞寁夋傪偨偰傞
- 娔嵏偲曬崘 僾儘僙僗俋丂儗億乕僩傪梡堄偡傞
丂丂丂丂丂 僾儘僙僗10丂儗億乕僩傪娔嵏偡傞
丂丂丂丂丂 僾儘僙僗11丂儗億乕僩傪岞昞偟丄僼傿乕僪僶僢僋傪庴偗傞
- 杽傔崬傒丗 僾儘僙僗12丂僔僗僥儉傪峔抸偟丄杽傔崬傓
乮3乯AS8003丂婇嬈偺幮夛揑愑擟
僆乕僗僩儔儕傾婯奿嫤夛偑嶌惉偟偨婇嬈摑帯偵娭偡傞婯奿僔儕乕僘AS8000乣8004偺侾偮偱偁傞丅婇嬈慻怐偺拞偱岠壥揑側CSR僾儘僌儔儉傪妋棫偟丄幚巤偟丄塣梡偡傞偨傔偵晄壜寚側梫慺傪採帵偟丄偐偮丄偙傟傜偺梫慺傪妶梡偟偰偄偔嵺偺僈僀僟儞僗偲偟偰嶌惉偝傟偨傕偺偱偁傞丅偙偙偱偼丄慻怐偺帠嬈妶摦偵娭楢偡傞CSR偺栤戣媦傃愑擟偺椞堟偲偟偰師傪娷傫偱偄傞丅
- 廂塿惈丄嫞憟揑姷峴媦傃壙奿愝掕丄
- 僈僶僫儞僗乛椣棟丄晠攕乛憽榙乛惌帯專嬥
- 廬嬈堳娭楢偺栤戣
- 嫙媼嬈幰娭楢偺栤戣
- 寬峃媦傃埨慡
- 娐嫬塭嬁
- 庴偗擖傟懁抧堟幮夛傊偺塭嬁
- 僐儞僾儔僀傾儞僗僔僗僥儉
- 棙奞娭學幰偺摿掕媦傃棙奞娭學幰偲偺媍榑
3.3丂儂僢僩儃僞儞乮拲栚傪堷偔廳梫巜昗乯
CSR梫媮帠崁偺拪弌偵偍偄偰偼丄埲壓偺崁栚偵偼丄廫暘偵棷堄偡傋偒偱偁傞丅偙傟傜偵懳偟偰偼丄僗僥乕僋儂儖僟乕丒僌儖乕僾偑乽慡抜敳偒戝尒弌偟乿偲偡傞傕偺偱偁傝丄儊僨傿傾傕拲栚偡傞丅偙偆偟偨巜昗偼婇嬈偵僀儞僷僋僩傪梌偊傞壜擻惈偑戝偒偔丄楻傟側偔娗棟偟側偗傟偽側傜側偄丅
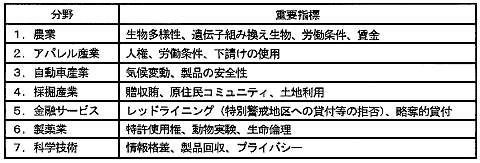
3.4丂巜昗慖掕忋偺棷堄帠崁
CSR偵娭偡傞巜昗丒婯奿偼悢懡偔懚嵼偡傞丅偟偐傕丄偦偺撪梕偼丄僗僥乕僋儂儖僟乕偦傟偧傟偺壙抣娤傪昞偡傕偺偲偟偰懡條偱偁傞丅慠傞偵丄屄乆偺巜昗傪尒傞偲丄昞尰偺嵎偼偁偭偰傕嫟捠偡傞偲偙傠傕懡偄丅偙偺揰偵拝栚偟偰丄巜昗饪偄暘偗丄偦傟傜偺悢偵埑搢偝傟側偄偙偲偑娞怱偱偁傞丅
傑偨丄偙傟傜偺巜昗偵懳偡傞擔杮婇嬈摿桳偺懳墳搙崌偄偺嫮庛傕擮摢偵抲偔偲傛偄丅
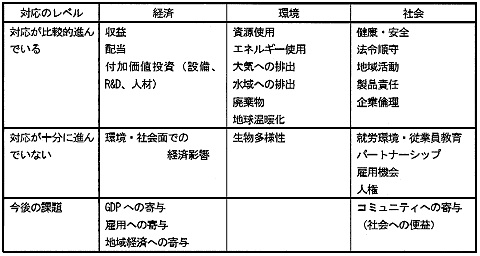
係丏CSR儅僱僕儊儞僩
CSR儅僱僕儊儞僩偼丄婇嬈偵偍偗傞儕僗僋儅僱僕儊儞僩偺堦娐偱偁傝丄僗僥乕僋儂儖僟乕偵儕僗僋偺徟揰傪峣偭偨傕偺偲偄偊傞丅廬偭偨丄儕僗僋儅僱僕儊儞僩偺僾儘僙僗偵懃偭偰恑傔傞偙偲偑戝愗偱偁傞丅
4.1丂帠徾擣幆
儕僗僋傪擣幆偡傞偨傔偵偼婇嬈偺栚揑傪柧妋偵偟側偗傟偽側傜側偄丅峏偵丄偦偺栚揑偑婇嬈撪偵嫟捠擣幆偲偟偰怹摟偟偰偄側偄偲婡擻偟側偄丅偦偺偨傔偵偼丄幮撪娭學幰傪慡柺揑偵摦偐偟丄嫵堢傪峴偄丄CSR偵懳偡傞峀斖側巟帩婎斦傪慻怐慡懱偵傢偨偭偨抸偔昁梫偑偁傞丅
- 僩僢僾偑丄婇嬈栚揑傪柧傜偐偵偟丄偦偺拞偱CSR懱惂峔抸偺柧妋側巜椷傪嶌惉偡傞丅
- CSR偵偮偄偰庢掲栶夛丄CEO丄宱塩姴晹僠乕儉傪嫵堢偡傞丅
- 庢掲栶夛丄CEO媦傃宱塩埾堳夛儗儀儖偺巟墖偲娭梌傪柧妋偵偡傞丅
- 慻怐慡懱偵傢偨偭偰CSR偺娭怱傪惙傝忋偘傞丅
4.2丂儕僗僋昡壙乮尰忬昡壙乯
CSR偵懳偟偰偼偳偺傛偆側曽恓傗寁夋丄峔憿偑婛偵幚巤偝傟偰偄傞偐丄偳偙偵嬻敀偑懚嵼偡傞偐丄偵偮偄偰尰忬懱惂傪憤崌揑偵昡壙偡傞丅
- 尰嵼偺CSR偺掕媊(擣幆)傪昡壙偡傞丅
- 尰峴偺CSR偵偮偄偰偺曽恓丄婯弨丄壙抣娤丄媦傃價僕僱僗尨懃傪昡壙偡傞丅
- CSR偵娭偡傞尰嵼偺岞栺丄椺偊偽嵦梡傑偨偼惀擣偟偰偄傞奜晹婯弨傪棟夝偡傞丅
- CSR偵娭梌偟偰偄傞晹栧丄怑擻丄傑偨偼怑擻墶抐宆慻怐傪摿掕偡傞丅
- 僒僾儔僀僠僃乕儞傪娷傔丄尰嵼庢傝慻傫偱偄傞CSR偺壽戣傪摿掕偡傞丅
- 僗僥乕僋儂儖僟乕偲偺娭學恾傪嶌惉偡傞丅
- CSR偵娭偡傞尰嵼偺寁夋媦傃妶摦傪昡壙偡傞丅
- CSR偺幚巤丄曬崘妶摦傪昡壙偡傞丅
4.3丂儕僗僋乮僗僥乕僋儂儖僟乕乯僿偺懳墳
摿掕偟偨僗僥乕僋儂儖僟乕偺億乕僩僼僆儕僆暘愅傪峴偄丄摉柺偺懳徾憡庤偲偦傟傜偵懳偡傞庢傝慻傒傪柧傜偐偵偡傞偙偲偑僗僥乕僋儂儖僟乕丒僄儞僎僀僕儊儞僩偺僉乕丒億僀儞僩偲側傞丅
- 婇嬈偵偲偭偰庡側僗僥乕僋儂儖僟乕偼扤偐
- 偦傟傜偺僗僥乕僋儂儖僟乕偺帩偮壽戣偲婇嬈偲偺娭學偼偳偺傛偆側傕偺偐
- 婇嬈偑嵟傕廳梫帇偟側偗傟偽側傜側偄愴棯揑側僗僥乕僋儂儖僟乕偼偳傟偐
傪柧傜偐偵偡傞偙偲偵傛偭偰斵傜偲嫤摥偡傞曽嶔傕嬶懱壔偟偆傞丅
側偍丄暘愅偼埲壓偺庤弴偵偰恑傔傞丅
仭僗僥乕僋儂儖僟乕偺摿掕
- 婇嬈偺庡梫側僗僥乕僋儂儖僟乕丒僌儖乕僾媦傃僌儖乕僾撪偺慻怐偁傞偄偼僙僌儊儞僩偺儕僗僋傪嶌惉偡傞丅
- 僗僥乕僋儂儖僟乕懁偺娭怱傑偨偼奣擮偵娭偡傞忣曬傪廂廤偡傞丅
- 僗僥乕僋儂儖僟乕偲婇嬈偲偺娭學傪惍棟偡傞丅
摿偵幮撪偺偳偺晹栧偲楢棈傪庢傝崌偭偰偄傞偺偐丄偁傞偄偼岎棳娭學偑偁傞偺偐丅
偦偙偱偺岎棳偐傜摼傜傟偨忣曬偼丄幮撪偱偳偺傛偆偵巊梡偝傟偰偄傞偺偐柧傜偐偵偡傞丅
仭僗僥乕僋儂儖僟乕偺昡壙
- 抦幆悈弨丗斵傜偺娭怱丄寽擮傪帩偮暘栰偵懳偟偰偳偺掱搙偺愱栧抦幆傪帩偭偰偄傞偐丅
- 塭嬁椡丗斵傜偺峴摦偑丄婇嬈丒嬈奅偺姷峴丄岞嫟惌嶔丄棫朄丄傑偨偼儊僨傿傾庢嵽
偵丄偙傟傑偱偳偺掱搙塭嬁傪梌偊偰偒偨偐丅
- 傾僾儘乕僠儍價儕僥傿(嬤偯偒傗偡偝)偲娭怱偺掱搙丗斵傜偼婇嬈偲偺岎棳偵娭怱偑
偁傝丄偦傟偵傛傞塭嬁傪庴偗擖傟傞偐丅
- 怣棅惈丗斵傜偼丄懠偺僗僥乕僋儂儖僟乕傗愱栧壠偵傛偭偰偦偺峴摦(巇帠)偑昡壙偝
傟偰偄傞偐丅儊僨傿傾傗懠偺婇嬈偼丄斵傜傪偳偆昡壙偟偰偄傞偐丅
- 儕僗僋偺愽嵼惈丗斵傜偼丄偳偺傛偆側堄枴偱丄愽嵼揑儕僗偲側傝摼傞偺偐丅
- 愴棯揑乛挿婜揑僷乕僩僫乕僔僢僾偺愽嵼惈丗斵傜偼丄婇嬈偲惗嶻揑側娭學傪抸偔偙偲偵娭怱傪帩偭偰偄傞偐丅偦偺揰偵偮偄偰懠偺婇嬈偲偺娭學偵偍偄偰偼偳偆偐丅
仭僗僥乕僋儂儖僟乕偺娭怱
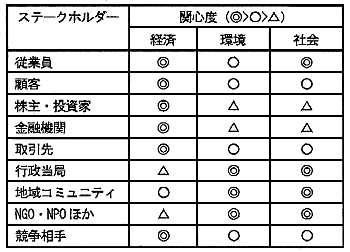
4.4丂摑惂妶摦(懱惂峔抸丒塣梡)
CSR儅僱僕儊儞僩僔僗僥儉塣梡懱惂偺峔抸傪峴偆丅懱惂偺専摙偵摉偨偭偰偼丄婲嬈偺巊柦傗婯柾丄妶摦暘栰丄婇嬈暥壔丄帠嬈峔憿丄抧棟揑忦審丄儕僗僋暘栰丄岞栺斖埻傪峫椂偵擖傟偰峔抸傪恑傔傞丅
傑偨丄CSR偼丄壽戣偑懡婒偵榡傝丄幮撪娭學晹栧傕懡偄偙偲偐傜丄慻怐墶抐揑懱惂偺峔抸偲丄慡懱傪摑惂偟偆傞埾堳夛慻怐丒僩僢僾儕乕僟乕偑晄壜寚偲側傞丅
|