





|
2005.11【特集記事-本誌編集部より-】 日産九州工場、九州池田電機、オムロン直方 工場見学付セミナー体験記
|
|||
1.日産九州工場 見学セミナーエモーショナルキャピタルが支える工場ロイヤリティと情熱が支える現場、そして品質 台風一過、青空が広がった9月8日。日産九州工場の見学セミナーが開催された。新技術開発センターでは「百聞は一見にしかず」との考えから工場見学付きのセミナーを数多く開催している。日産は追浜工場での開催があるが、九州工場は初めてである。 このセミナーの趣旨は同期生産をいかに築きあげるか、そのノウハウと工夫を学ぼうというもの。工場見学に加え、コンサルタントの上野直紀氏から生産改善の考え方を講義、日産全体がどのような考えでNPWを推進しているかを本社のNPW推進室主査・武尾祐司氏が解説、それを実現するための人材教育や工場マネジメントを日産九州工場生産課の課長がポイント講義するなど、充実した内容が企画されていた。 日産九州工場が生産しているのはティアナ、プレサージュ、ラフェスタ、ブルーバードシルフィ、ムラーノ、エクストレイル、プリメーラ、プリメーラワゴン。4600人が敷地面積23万6200m2で働いている。品質確保、環境保護への取り組みも先進的だが、地域との融合を目指し、広場をつくり家族で参加できるイベントを開催したり、積極的に工場見学を受け入れたりしている。 この日産九州工場は75年に操業開始した。エンジン工場を増設、また一世を風靡したシルビアの生産拠点となった。シルビアの販売にあたっては工場から東京まで社員が運転、シルビア販売キャンペーンとして大成功した実績も持つ。 92年「夢工場」として第二工場が建設される。高齢者や女性にも働きやすいライン、無理のない姿勢で作業性をアップさせるとともに品質を確保するというこの第2工場のポリシーは現在も脈々と受け継がれている。 今回、見学したのはこの第2工場。1ラインに複数車種が流れる混合生産が行われている。このメインラインで流れる車のフレームには紙が張られており(いわゆるカンバン)、いつ納車するのか、どんなオプションがつくのかといった情報に加え、すでにお客様の名前が書いてある。また、ディーラーオプションもこの段階で発注されており、納車と同時にディーラーに届くようになっている。 このメインラインにサブラインから供給する部品は当然、車種によって異なる。流れてくる車種にあわせ、どうやって部品を誤りなく供給するか。ここが大きなポイントになる。情報とモノの流れ、そして、その情報にあわせてつくる能力、それを支える部品供給や配膳方法といったところも参考になる。 そして、完成車は自社専用バースにつけられ、船積みされる。 ところで、ここで流れる車種が違うのは当然だが、艤装(組み付け)方法も異なる。というのは、新しい技術は新車から取り入れられていくため、旧車種と新車種があれば作業が異なるためだ。たとえば、モジュール化。最新車種はフロントエンドモジュールとなっており、車体組み立ての段階ではフレームがない。したがって、作業者が部品を組み付けるときにフレームを越えて取り付ける作業はなく、取り付け場所に入り込んで作業ができる。したがって、腰をかがめることなく楽な姿勢ででき、作業性もアップ、これが品質の向上にもつながっている。 同社では全社でダイバーシティに取り組んでおり、女性の数を増やしている。九州工場でもラインも含め全従業員の4%の女性化を目標にしている。すでにラインではてきぱきと作業を進める女性の姿も目につき、一部職域では目標をクリアしているという。女性をラインに配するためには治工具の工夫や重量物運搬の改善など、企業が取り組まなければならない課題も多い。九州工場でもかなりの工夫をしており、この点でも見るべきところは多いといえよう。 こうした一連の取り組みはそこで働く人の自社への想いと製品へのプライドに裏づけされている。講師の上野氏が「事業資産、ビジネスキャピタル、インテレクチャルキャピタル(知的資産)に加え、第4の資産が注目されている。それがエモーショナルキャピタルだ。事業、ビジネス、知財があっても、それを使い、育て、やり遂げようとする情熱や心がなければ、成功しない。その部分を学び、自社で展開するときにも持ってほしい」と締めくくった。 なお、日産九州工場では車が展示され、生産過程をデジタルで楽しめるゲストホールや屋外のさわやかな風を楽しみながら弁当を楽しめるドリームパーク23もある。当日は社会科見学にきた小学生が走りまわっていたが、ピクニック気分で訪ね、「モノづくり」に触れるのも楽しそうだ。 2.天草池田電機、オムロン直方工場目に見えないムダまでも発見し、ムダを最大限排除─生産性向上、在庫低減に大差がでる生産革新の成果─ ●天草池田電機● キラリと光る小さな工場。組立がメインの現場では全員が改善の担い手セ。価格競争に負け、撤退が決まった工場が現場の力でよみがえった。
天草池田電機はオムロンが同社の前身であるオムロン天草が撤退を決定したときに、MBO=マネジメント・バイ・アウト 経営陣による買収)によって生まれ変わったマグネットリレーの生産工場。 海外へのシフト、競争力の低下といった現状から撤退を決めたオムロンだが、ここを立て直すには1にも、2にもコストダウンしかない。トップの強い意志のもと、一致団結して改善に改善を重ね、競争力のある製品づくりを行ってきた。組立工程がメインとなるが、「技術と情熱を結集し、お客様に安心してお使いいただける製品を作りつづけ、地域社会に貢献します」という社是にあるように、個々人がそれぞれの持ち場で情熱を傾けている。  最近では一般消費者向けの自社製品としてサッシ用防犯ブザー「るすばん君」を開発・販売、部品メーカーの悲願でもある「自社製品を持つ」も叶えた。
最近では一般消費者向けの自社製品としてサッシ用防犯ブザー「るすばん君」を開発・販売、部品メーカーの悲願でもある「自社製品を持つ」も叶えた。同社の一連のコストダウン、企業再生の取り組みは地元でも有名であり、地元テレビ局のドキュメンタリーとしても取り上げられている。 ここでは、一通りの工程を見学した後、ムダ排除の目の付け所やポイントを講義した後、もう一度、その視点で該当する工程を見学した。 ●オムロン直方● 機械化が進んだ工場。ここでのムダ排除は機械と人とのバランスと不良の削減になる。  プリント基板、電子機器製造を行うオムロン直方。110600㎡の敷地に197名が勤務している。この面積でこの人数、すぐに無人化が進んだ工場であることが見て取れる。企業哲学も「機械にできることは機械にまかせ、人はより創造的な分野での活動を楽しむべきである」だ。
プリント基板、電子機器製造を行うオムロン直方。110600㎡の敷地に197名が勤務している。この面積でこの人数、すぐに無人化が進んだ工場であることが見て取れる。企業哲学も「機械にできることは機械にまかせ、人はより創造的な分野での活動を楽しむべきである」だ。66年設立、1969年には世界最小12桁卓上電子計算機を生産、71年形61F液面制御機器生産開始、82年クレジットカード認証端末生産開始、89年プリペイドカードターミナル生産開始と時代の最先端製品を生産してきた。いまでは自社製品のほか、試作から量産までを行ったり、ノウハウを活用したソリューションを提供したりといったEMS事業を展開している。 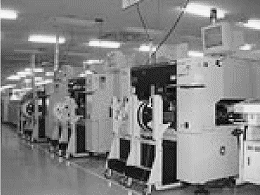 概要を見ると分かるとおり、ボリュームもさまざまであれば、仕様もさまざま。しかもそれが似ているといった製品が作られている。こうした状況で機械化をすすめるためには、生産計画の工夫が欠かせない。他方、現場では情報とモノが一致すること、可動率を限りなく100%にしておくこと、不良が出さないようにすること、不良がでたときに機械が止まり、そのものが次工程に流れないようにすること…といった知恵を機械に持たせる必要がでてくる。
概要を見ると分かるとおり、ボリュームもさまざまであれば、仕様もさまざま。しかもそれが似ているといった製品が作られている。こうした状況で機械化をすすめるためには、生産計画の工夫が欠かせない。他方、現場では情報とモノが一致すること、可動率を限りなく100%にしておくこと、不良が出さないようにすること、不良がでたときに機械が止まり、そのものが次工程に流れないようにすること…といった知恵を機械に持たせる必要がでてくる。さらに、機械と機械のつなぎ、機械と人とのコンビネーション(仕事の分担や段取りなど)をどのように考えるかといった課題が見えてくる。 組立工程がメインといっても、機械との共存は避けて通れない。自社での機械化の方針や共存方法、効率的な機械の使い方の参考になるに違いない。 |


