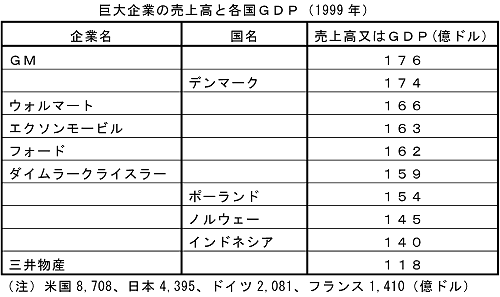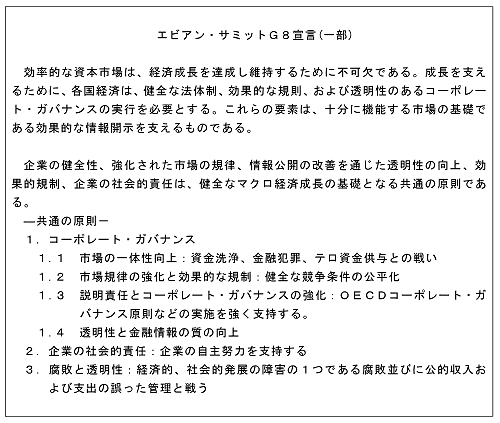| |
 |
2006.01【特集記事−CSR】
2006年,CSR(企業の社会的責任)の時代が始まった
−CSRを理解するためにイメージしよう−
吉澤経営研究所 所長
技術士 経営工学部門
吉澤 光男
|
| |
 |
はじめに、「CSR(企業の社会的責任)とは何か」、「今、なぜCSRがとり沙汰されるのか」について理解を深めるべく、現在議論の対象になっているCSRの定義・概念について説明します。
また、CSRに該当する行為は、新しいものではないことを知るべく、CSRの歴史を紹介します。加えて、CSRの国際標準化に向けたISO(国際標準化機構)の動向と、これを睨みながらの各国でのCSRへの取り組みを紹介します。
更には、CSRは一時的なブームではなく、強力な時代の変化に後押された国際的な波であることの認識が必要です。特に、EUにおける国家的なCSR支援、社会的責任投資(SRI)の拡大は、CSRの今後を見通すうえでも大切です。
1.CSRの定義
CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)という言葉をここ数年耳にすることが多くなった。しかし、これに該当する行為は古くから行われており、決して新しいものではない。
CSRの初期の活動形態は、宗教倫理あるいは慈善的な色彩を伴うものであったが、企業活動が社会生活に与える影響力が増大するにつれてフィランソロピーやメセナ活動に対する期待に応えるものへと拡大されてきた。近年では、企業活動のグローバル化に伴い、経済的視点のみならず環境的・社会的な視点も備えた「よき企業市民」として社会と共存を進めるべく企業活動を律するものとする概念が有力になってきた。
然るに、企業が社会との共存を図るにおいても、企業を取り巻く社会が企業に寄せる期待観・価値観は、一国内においてすら利害関係者(ステークホルダー)各層によってさまざまであり、これに民族、風土、国家、宗教などのグローバルな要素が加わるとCSRの概念は多様なものとなる。
これゆえに、CSRについての精力的な議論は行われているものの、国際的な統一概念を作り上げるにはいたっていない。
よって、CSRに取り組む第一歩として、以下の諸団体による定義を参考にしながらCSRのイメージを固めていくことにしたい。
- CSRとは、責任ある行動が持続可能な事業の成功につながるという認識を企業が深め、社会環境問題を自発的にその事業活動及びステークホルダーとの相互関係に取り入れるための概念をいう(欧州委員会指令:グリーンペーパー)。
- CSRとは、社会が企業に対して抱く法的、倫理的、商業的もしくはその他の期待に照準をあわせ、全ての鍵となる利害関係者の要求に対しバランスよく意思決定することを意味する(BSR:Business for Social Responsibility、米国のCSR推進市民団体)
2.CSRに包含される要素
CSRの定義は抽象的であることから、具体的な取り組みに際しては、CSRを要素別に展開する必要がある。
CSRのキーワードをイメージする上で、以下の例から有効な示唆が得られる。
(1)ISO高等諮問委員会答申リポート
CSRに関するISO高等諮問委員会答申リポート(2004年4月)の付属書Aには、同委員会にてCSR議論の対象とされた次の事項が列挙されている。
- 取引活動:公正取引、倫理的な広告宣伝、市場乱用の無効化、市場支配
- 反競争的行動:原産地表示規定
- コーポレート・ガバナンス:規定化されたコンプライアンス・システム、経営会議体の構成とインテグリティ、透明性のある報告と説明責任、リスクマネジメント、内部監査システム、知的財産の保護、反詐欺的な手法、内部告発者の保護
- 雇用:機会の平等、公平な給与と条件、団結の自由の保障、被差別的な採用と昇格、児童労働の回避、強制労働の回避、合理的な懲戒処分、合理的な労働時間と条件、個人プライバシーの保護、紛争・課題の公正かつ非差別的な解決の手法、内部コミュニケーションの手法
- 製品管理責任:リサイクル/リユース適合設計、エネルギー効率、非有害な素材と製造工程、環境負荷の最小化、製品リサイクル、製品処分/廃棄物管理
- 取引関係:倫理的な調達行動、入札談合の回避、価格カルテルの無効化
- 健康と安全:安全な労働作業、安全な労働環境、職業衛生、職場設備、障害物・危険物の管理、生命工学、緊急時の備え、公平な労災補償、回復訓練、職場回復プログラム
- 環境保護/サステナビリティ:持続可能な生産、エネルギー消費の削減、廃棄/排出のマネジメント、植物/動物/文化遺産の保護、ステークホルダーとの対話/連携
- 良き企業市民:社会の良き行動への貢献、事前活動、組織の説明責任、社会性報告、不正・賄賂の排除
(2)経済産業省「企業の社会的責任に関する懇談会」中間報告
わが国の例では、企業の社会的責任に関する懇談会(座長:伊藤邦雄一ツ橋大学商学部長)の中間報告書における集約意見としてCSRの概念が以下のように提示されている。
- CSRは、さまざまなステークホルダ(消費者、従業員、投資家、地域住民、NGO、など利害関係者)との交流の中で実現される。
- CSRは、企業外とのコミュニケーションにとどまらず、企業内における組織体制の構築なども含まれる。
- CSRは、最低限の法令順守はもとより、事業と密接な関係を有する製品・サービス市場の安全確保、地球環境・廃棄物リサイクル対策を含めた環境保護、労働環境改善、労働基準の遵守、人材育成、人権尊重、腐敗防止、公正な競争、地域貢献など、更には地域投資やメセナ活動、フィランソロピー(社会貢献)、などさまざまな活動に及ぶ。
- CSRは、国や地域の価値観、文化・経済、社会事情によって多様である。
- CSRの内容・取組みに関しては、企業の自主性・多様性と戦略的取り組みが重要である。
- CSRの信頼性を支える取組みの中で最も重要なものは、情報開示と説明責任、ステークホルダーによる評価とステークホルダーとの対話である。
以上から分かるように、CSRに包含される要素の範囲は極めて広い。
従って、自社の経営基盤、自社に対するステークホルダーの期待などを経営戦略的に勘案し、リスク管理の視点から管理項目、管理水準、管理方法を明確にしていくことが大切である。
3.CSRの歩み −CSRには歴史がある−
(1)欧米における歩み
CSRのルーツとなる活動は、18世紀に慈善寄付行為として始まったが、時代の要求を受けさまざまな変遷を経つつ現在にいたっている。
- 18世紀の英国でQuaker Lead Companyが自社の労働者の満足度を向上させるために町づくり、学校、図書館の建設を行っている。但し、当時としてはこうした企業の活動は、あくまでも例外的なものであった。
米国では、鉄道会社が沿線に学校を寄付するなどの例が見られ、企業による寄付行為は、地域住民に対する支援に企業が積極的に取り組む形で進められた。
- 1920年代、教会の資金を運営する際に、タバコ、アルコール、ギャンブルなど、その教義から許容し難い業種を投資対象から外す運動が始まった。これは現在のSRI(Socially Responsible Investment:社会的責任投資)の草分けとなるものである。
SRIは、その後投資先の選択に止まらず、社会運動に基づく株主行動へとエスカレートした。
- 1960年代以降、米国では、公民権運動、反アパルトヘイト運動や反戦運動が盛り上がり、株主行動が注目されるようになった。
その顕著な例を挙げると、ベトナム戦争で使用されたナパーム弾製造会社のダウケミカル社に、その製造中止を求める株主提案が行われた。
GM社においては、アパルトヘイト政策を行っている南アフリカからの事業撤退を求める株主提案が提出された。
- 1990年代になると、兵器、タバコ、アルコール、ギャンブルのみならず、雇用の機会均等や女性・マイノリティに関する人権問題、動物実験なども加わり、反社会的行為の範囲も更に拡大された。
その一方で、「企業の環境対策は企業価値にとってプラス」という環境経営の考え方が広まったのを契機として、マイナスイメージ評価に限定することなく、プラスイメージの企業評価も積極的に行われるようになり、企業価値評価にはCSRの観点が必要との考え方が浸透してきた。
90年代半ば以降になると米国では、確定拠出型年金の401Kプランの選択メニューにSRIが取り入れられるようになって、SRIは急速に拡大した。
- 2000年に入ると、欧州では、EU統合による各国間の地域経済格差の拡大を防止する役割を企業行動に求め、同時に行政が法制度改革などによるSRI支援に向けた積極的な介入姿勢を見せるようになった。
(2)わが国での歩み
わが国におけるCSRは、取引・企業活動における倫理として唱えられ、その実践に範を遺した「篤志家」も多い。
現在でも、企業倫理を社是・社訓に掲げている企業は多く、企業を社会的存在と位置づける見方は少なくない。
- 近江商人の家訓に「三方よし(売り手によし、買い手によし、世間によし)」が残されている。
報徳思想で知られる二宮尊徳は、「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は寝言である」という言葉を残している。
これらは経営とCSRとの関係をよく表している。
- 明治・大正の実業家で、日本資本主義の先駆者である渋沢栄一は、「事業という以上は、自己の利益とすると同時に社会・国家をも益することでなくてはならぬ」と説いている。
- 戦後の高度経済成長期から現在に至るまでにおいても「社会に対する経営者の自覚と実践」が繰り返し唱えられて来た。
しかし、戦後の混乱から産業の回復・発展が進むとともに企業活動による公害が深刻になり、更には、第一次石油危機において、買占め・便乗値上げが世間を騒がせた。
最近でも下表の如くそれぞれの業界で企業不祥事が後をたたない。
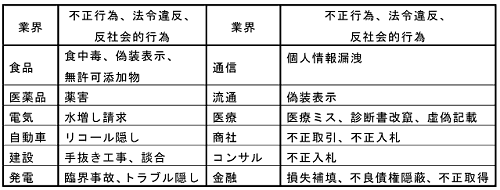
- わが国のNGO/NPOは、欧米と比べて強力な発言権をもってCSR活動を展開するまでには育っていない。これは、行政と企業との結びつきが強いという歴史的な経緯や税制措置などの遅れに起因している。
- 近年、わが国企業の活動がグローバル化するにつれ、国外での資金調達、資材調達、生産、販売が盛んになるにつれ、欧米の価値基準やルールに直面することが多くなり、これらが避けられないCSRの波としてわが国に押し寄せている。
4.CSRの推進力−CSRは一過性の波ではない−
CSRは、一時的なブームとしての活動ではなく、大きな推進力に支えられた国際的な動きである。
この背景を十分に理解して、国際的に遅れをとらないことが肝心である。
CSRの国際的な推進力として、次のような時代の変化があげられる。
(1)企業活動領域の拡大
最大の要因として企業活動の規模の拡大・複雑化があげられる。
多国籍企業に代表されるように企業活動がグローバル化すると、進出先の国の経済、環境、雇用、さらには国家主権にまで進出企業が影響を与える。この結果、社会の隅々にまで企業活動のインパクトが無視できない大きさで及ぶようになった。
下表の如く、一国のGDPを凌駕する売上げ規模を持つ国際企業は少なくない。
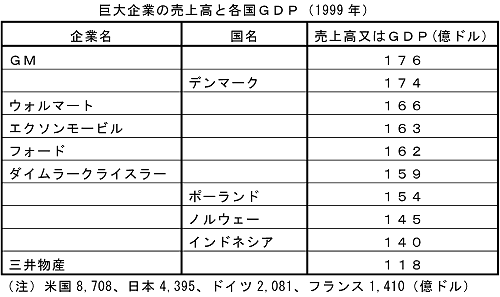
その結果、発展途上国における不完全な法規制の下では、児童労働・搾取労働、環境破壊などが発生しやすくなる。
また、地球規模での取引が拡大するにつれ、国外のサプライヤーが問題の起因となるケースも目立つようになり、この場合にも直接親会社に対して責任が問われる。このように、企業を取り巻く社会的責任の範囲は、サプライチェーン全体をも取り込み拡大する一方である。
(2)IT化の進展
IT技術の進歩は、情報の瞬時世界伝播を可能にし、グローバル・レベルでの企業活動の監視を可能にした。
また、共通の課題に関心を持つステークホルダーが、NGO、個人を問わず、インターネットを通してネットワーク化され、企業評価情報がグローバルに関係者間で共有されることになった。
更には、ITの普及により、メディアを通さずとも、ステークホルダーが直接社会に対して情報発信することが可能になった。
(3)NGO/NPOの影響力の拡大
欧米では、NGOによる反社会的行為の追及が巨大なグローバル企業の行動を直撃し、「企業のあるべき視点に立った行動」の見直しを求めるまでにいたっている。
- ベトナム戦争反対の立場から、ダウ・ケミカル社にナパーム弾製造の中止要求。
- GMに対して人種隔離政策を続ける南アからの事業撤退要求。
- ハーバード大学に対して、黒人差別国にて操業するガルフ石油株の売却を要求。
- アラスカにおけるエクソンモービル社のタンカー座礁による原油流出事故を受けて米国環境保護グループCERESがバルディーズ原則(セリーズ原則に改定)を発表。
- シェル石油会社が国の許可の下で行おうとした石油掘削プラットフォーム海洋投棄に関する抗議運動。
- 進出先のベトナムにおける児童労働放置を理由にナイキ製品の不買運動。
- 米国の遺伝子組み換え食品の欧州市場からの締め出し。
- アメリカン・ブリティシュ・タバコ会社に対し、ケニアやブラジルにおいてタバコ栽培農家の保護具なしの殺虫剤散布作業を放置し、農民に慢性疾患が発生したことを追及。
- シェル石油会社に、ナイジェリアにおけるパイプラインの油漏れ放置を追及。
- コカ・コーラ社に対し、進出先の南インドにて井戸の水枯れ発生を追及。
(4)グリーン・コンシューマリズム
NGOが、独自の規準で企業を評価し、ネガティブ/ポジティブ情報を消費者に流して、関係する企業の製品の不買を訴え、あるいは購入を推奨する活動が大きな影響力を持つに至っている。その例を次に示す。
- CEP(Council on Economic Priorities:経済優先順位研究所)
NGO組織として69年にニューヨークで設立された。その活動は社会環境的観点から企業を評価し、4段階に格付けして、消費者などにその情報を提供するものである。
格付けの結果は、「Shopping for a Better World」を刊行して公表している。
そこでの評価は、次の7項目からなる。
- 環境
- 女性の登用
- マイノリティの登用
- 寄付
- 労働環境
- 家族の福利
- 情報開示
- Co-op America
82年にワシントンD.C.で設立されたNGOで、消費財生産会社約350社の情報をウエブサイトで提供している。そこでは、次の情報が、詳しく提供されている。
- 企業格付け評価
- 社会・環境関連事項での企業の賞罰履歴
- グループ企業
- ブランド など
(5)SRI(Socially Responsible Investment)の影響力の飛躍的拡大
SRI(社会的責任投資)は、そもそも、キリスト教宗教団体が、その倫理観に見合った資金運用をすべきという価値観からスタートしたものである。これに社会をよくするために何らかの行動をしたいとの能動的な市民意識が加わり、この価値観・意識に賛同する市民、あるいは組織が、市場メカニズムを活用して保有資金を投資運用するものである。
このような活動を通して企業にプラス/マイナスの裁可与えることによって、社会的に責任ある行動を企業に促す新しい規範が市場で形成されてきた。
SRIが企業に与える影響力は、資金調達などの面において益々強力になっていくことが予想されることから、SRIについては十分な理解が必要である。
1)SRI投資活動
SRI投資活動は、つぎの3種類に大別できる。
- スクリーニング
- ネガティブ・スクリーニング:アルコール、タバコ、ギャンブルなどを社会的に好ましくないとして投資対象から除外するもの
- ポシティブ・スクリーニング:倫理、コンプライアンス、環境対応、社会貢献など、企業に取組み強化を期待する事象を規準にして投資対象を選定するもの
- 株主行動
経営陣との対話:CSRに関する取り組みを改善するように、株主として経営者に直接働きかける、あるいは議決権を行使するもの
- コミュニティ投資
荒廃した地域、低所得者層の居住地域の改善や経済的発展のために再開発資金の提供などを行うもの
なお、最近では、以下も含まれる。
- ソーシャルベンチャー:社会問題の解決につながるビジネス(再生可能エネルギー、有機食品など)へのベンチャーキャピタル
2)スクリーニングの規模
各国のスクリーニング運用規模を以下に示す。
- 2003年における米国SRI市場の投資運用資産残高は2兆1750億ドル(約240兆円)、このうちスクリーニング運用は全体の99%の2兆1540億ドルに達する。これは総運用資産に対して11%を占める。
1995年のSRI運用資産残高が6,390億ドルであったことから、その伸びは、3.4倍(8年間)にも達し、驚くほど急激である。
- 欧州での2003年のSRI市場は3,482億ユーロ(45.5兆円)程度と推定される。このうち、オランダが1,814億ユーロ、英国が1,478億ユーロである。
- 日本で本格的なSRI運用が始まったのは1999年で、日興エコファンド、ぶなの森などの名前で売り出されたが、わが国のSRI投資信託の2004年3月末の総額は1,027億円に過ぎない。
3)株主権の行使
2003年における米国SRI市場の投資運用資産の20%にて株主権が行使されている。以下に米国の機関投資家・年金基金の2社の例を挙げる。
- カリフォルニア州公務員退職年金基金(CalPERS)
議決権行使の規準を定め、投資先企業に責任ある行動を求めて株主行動を行う。投資先には次の行動をもとめる
- 法令順守
- グローバル・サリバン原則(人権保護、強制労働、差別禁止等)及びマクブライド原則(労働者の権利など)の遵守
- 人権侵害の排除
- 従業員と家族の尊厳と幸福
- TIAA-CREF
(Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund)
「長期的な株主価値の向上は、投資先企業の取締役会が社会的責任と公共の利益を慎重に考慮することと一致する」との基本的な考え方を打ち出し、企業に次に対する方針の確立と実践とを求める。
- 企業の操業及び製品の環境へのインパクト
- すべての人口セグメントの雇用機会の平等
- 従業員教育と能力開発
- 地域社会の公共の利益にネガティブな影響を与える企業行動の評価
- わが国の年金基金の行動
- 厚生年金基金連合会
「株主議決権行使に関する実務ガイドライン」を策定し、議決権行使を通じた企業統治体制のチェックを開始(2001年10月)、更に国内株式の自家運用を開始した(2002年2月)。
- 地方公務員共済組合連合会
厚生年金基金連合会にならってガイドラインを制定し、議決権行使に乗り出した(2004年4月)。
4)SRI市場の拡大要因
米国SRI市場は、1995〜2003年までの8年間で3.4倍に拡大した。オランダでは、こ
の間に15倍に拡大。
英国では、1997年〜2001年の4年間で10倍となった。
このようにSRI市場が拡大した理由としては、次の要因があげられる。
- CSRに対する関心の世界的な高まり(前述)
- 資本市場の不祥事
米国におけるエンロン事件からワールドコムまでの一連の不正経理事件や投資信託の不祥事が資本市場に対する社会的信頼を揺るがし、投資家が「倫理的な経営を行っている企業の方が、リスクが小さく、リターンも大きい」とする傾向が強まってきた。
- 法的整備
- 英国では年金法が改正され(2000年7月)、企業年金の運用責任者に対して、社会・環境・倫理問題が投資方針の中で考慮されているか否か、されている場合は具体的な方針の開示が義務づけられた。
- フランスでは、新経済規制法(2001年)で、上場企業に対して社会・環境側面の情報開示を義務付けた。
- SRIインデックスの開発
先述したSRI投資要求に応じる体制としてSRIインデックスの開発が挙げられる。これによって、SRI投資信託を運用する際にインデックスのベンチマークができ、かつ、インデックスファンドを組成することも可能になった。
現在運用されている代表的なグローバル・インデックスには、次の3種類がある。
- Dow Jones Sustainability Group Index
- FTSE 4 Good Indexシリーズ
- Ethibel Sustainability Indexシリーズ
わが国のインデックス
- モーニングスター社会的責任投資指数(日本株を対象としたSRI指数)
(6)エビアンサミット宣言
2003年6月に開催された主要国首脳会議(エビアン・サミット)で、CSRは議題に初めて取り上げられ、「責任ある市場経済」宣言がなされた。
そこでは、資本市場が持続的な成長を達成するためには、先進国及び途上国における信頼性と信用とが重要な鍵であり、「企業統治の強化」「企業の社会的責任」「腐敗防止及び透明性の確保」が重要な要素となることを謳っている。
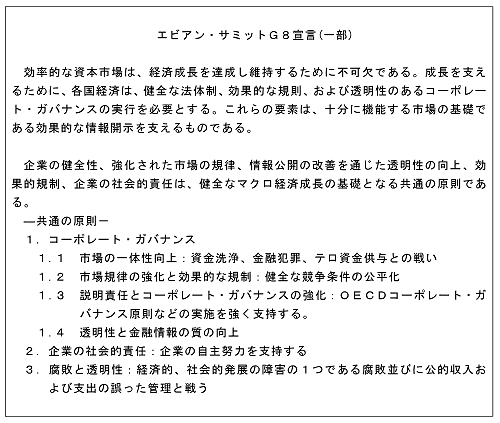
| |