





|
2006.10【特集記事−図説「目で見る管理」(8)】 設備、治工具の管理も簡素化 ポカヨケにもつながる一工夫
|
●1品種に13〜14種の印刷を重ねる工程デンソー高棚製作所のメータ印刷工程では1品種に13〜14種の印刷を重ねて製品が出来上がる。通常、紙へのカラー印刷は黒、赤、黄、青の4色を使用、それぞれの色ごとに版をつくる。たとえば赤は赤版で表現されている。同様に黒、黄、青の版があり、それぞれがその色だけで表されており、その組み合わせで表現する。 中間職は各版に濃淡があり、赤だけで表現するのであれば、赤100%、中間のピンクであれば50%、薄いピンクであれば20%などと表現し、紫であれば赤版と青版を組み合わせてつくる。 印刷を知る人であれば、この苦労は分かると思うが、印刷の版は同じ形をしている。 同じ機械を使うのであるから、当然といえば当然なのだが、それを版のズレがないようにするのは技術がいる。コンマミリメートル以下の狂いがあっても、色がズレてしまうからだ。こうなると、製品がにじんでいるように見えてしまい、商品価値がなくなる。 デンソーの場合、これが13〜14ある。これをぴったりと同じ場所にセットするのであるから、その位置決めノウハウは相当なものである。 ●コストをかけず、見やすく、分かりやすくところで、位置決めノウハウ以前にこの13種〜14種の版をどのように管理するのかが問題になるだろう。品種ごとにまとめて棚にいれるのが通常考えられる方法だろう。だが、それだけであると、そのセットのなかから1種類の版だけを補修したり、差し替えたりしたときに分からなくなってしまうことも出てくる。当事者だけが最初から最後までやるのであれば、そのようなことは起こらないのだろうが、そんなことはありえない。 そこで、気が利くところでは版に品番を書くことになる。こうすれば、1つだけを取り出しても、元の位置に戻せる。迷子になることもない。 しかし、元の位置に戻すまでに時間がかかる。暗いところで数字やアルファベットを読むのでは読み違いも起こりかねないし、書かれた文字、たとえばO、Qと0、Iと1、Pと9など判別しにくく、うっかりミスを誘発しそうである。 段取り替えでも品番を頼りにするとポカミスをしてしまいそうだ。 そこで、デンソーが行っているのがビニールテープによる色分けである。同じ品種の1セットごとに版の横に同色のビニールテープを貼るのである。同じ色になっているのだから、戻すときに間違えることはない。もし、違う色が入っていてもすぐに気づく。他部門の人が気づいても、このテープを手がかりにすれば、すぐに戻せるのだ。 段取り替えにしても、色を照合させていくのだから、早い。現場が判断をすることはない。単純な色あわせでできる。これならば、段取り替えの準備は新人でもできる。 5Sの定石として、事務所内の書類やファイルボックスに斜めにラインを引き、きっちりと戻すというのがあるが、これの応用と考えればいいだろう。事務所の場合は書類が主となっているので、マジックペンなどで線引きをするが、枠は木でできているので、マジックペンでは書きにくい。また、木ににじむため、色も分かりづらくなってしまう。そこで、活用されたのがビニールテープである。 さて、そのビニールテープだが、デンソーでは市販のビニールテープだ。色は赤、 黄、ブルー、緑、橙など。テープの色別で版を管理しているため、テープ自体の種類は多いが、どんなに種類をそろえてもコストは高が知れている。貼り直しも簡単にでき、追加があっても柔軟に対応できる。また、テープを貼るだけなので、必要なのもはさみだけといたってシンプルな仕組みとなっているのもいいところだ。 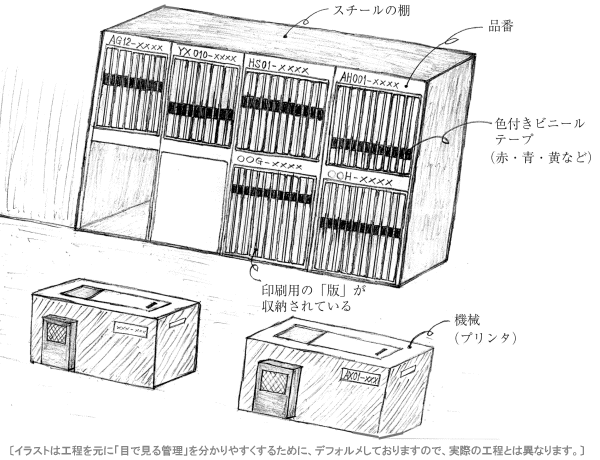
●シンプル イズ ザ ベスト 実を取る管理手法トヨタグループが行う「目で見る管理」というと、豊富なノウハウと実績、巨大な設備投資から洗練された仕組みやシステム、美しい姿かたちを思うが、実は目的がかなえられることが第一となっており、見た目に凝ったものは少ない。先回、紹介したダンボールを活用した表示や今回のビニールテープを使った版の管理など、そのツールはどこにでもあるものだ。1回目で紹介した時間を管理するラインサイドの白線にしても、どこの製造現場でも見られるものである。 ところが、その用い方に多くのノウハウが詰め込まれているところが他社と大きく違うところであろう。だれ(新人、通りがかりの見学者、突然現場に現れたトップ)にも分かる現場の状態をシンプルでどこでも入手可能な道具で、安価に実現している。 もちろん、バックには徹底した現場の改善活動や生産調査室による検証などがあるが、それを意識させないほど、粛々と現場は動いている。 ちなみに今回取り上げたデンソーの印刷工程には人影はほとんどない。こうした現場であっても、改善活動を行い、ミスをしないよう、分かりやすいよう工夫しているところに実力を感じるのである。
|


