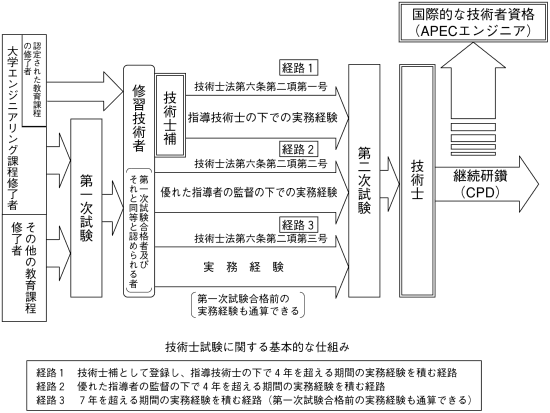| |
 |
2009.11【特集記事】
技術士新試験の内容は?
〜技術士試験の概要と最近の試験結果〜
| |
 |
1.技術士制度のあらまし
技術士は、およそ半世紀前に、米国のコンサルティングエンジニアおよびプロフェッショナルエンジニアの制度を倣って、コンサルティングエンジニアの制度を定着させるために生まれたものです。
当初民間資格としてスタートし、技術士法の制定をめざした積極的な活動が行われ、紆余曲折を経て1957年、国会の審議を通過し、科学技術庁を所管とする技術士制度が発足したわけです。
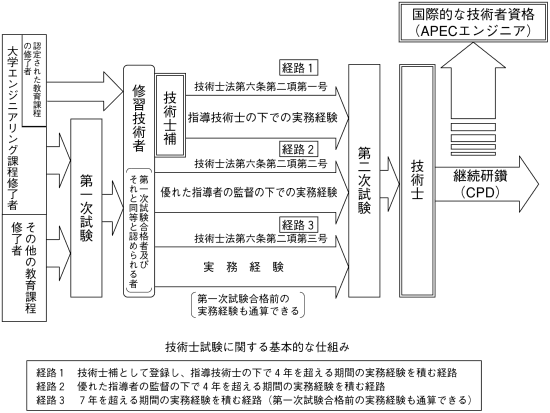 1958年7月、第1回目の技術士試験が行われ、同年11月、技術士法に基づく(社)日本技術士会が発足しました。
1958年7月、第1回目の技術士試験が行われ、同年11月、技術士法に基づく(社)日本技術士会が発足しました。
1983年には技術士補制度が発足し、技術士となるのに必要な技能を修習するため、技術士補として技術士業務を補助することになりました。
1998年に、APECエンジニアの枠組み作りがスタートし、2000年にAPECエンジニア登録が開始されました。この動きに伴い、2000年4月、技術士法が改正され、技術士第二次試験は技術士第一次試験の合格者(及びそれと同等と認められる者)のみが受験できるようになりました。技術士第一次試験は技術士第二次試験のパスポートというわけです。そして、2007年から第二次試験の試験方法が大きく改正されました。
2.技術士第一次試験実施概要(平成22年度は未発表)
平成20年12月24日に発表された「平成21年度技術士第一次試験実施大綱」によると次のようになっています。
1)技術士第一次試験の実施について
- 技術士第一次試験は、機械部門から原子力・放射線部門まで20の技術部門ごとに実施し、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び技術士法第四章の規定の遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要な技術部門についての専門的学識を有するか否かを判定し得るよう実施する。
- 試験は、基礎科目、適性科目、共通科目及び専門科目の4科目について行う。
出題に当たって、基礎科目については科学技術全般にわたる基礎知識(設計・計画に関するもの、情報・論理に関するもの、解析に関するもの、材料・化学・バイオに関するもの、技術連関)について、適性科目については技術士法第四章(技術士等の義務)の規定の遵守に関する適性について、共通科目については技術士補として必要な共通的基礎知識について、専門科目については技術士補として必要な当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識について問うよう配慮する。
試験の程度は、共通科目については4年制大学の自然科学系学部の教養教育程度、基礎科目及び専門科目については、同学部の専門教育程度とする。
- 基礎科目、適性科目、共通科目及び専門科目を通して、問題作成、採点、合否判定等に関する基本的な方針や考え方を統一するよう配慮する。
なお、専門科目の問題作成に当たっては、教育課程におけるカリキュラムの推移に配慮するものとする。
2)技術士第一次試験の試験方法
(1) 試験の方法
- 試験は筆記により行い、全科目択一式とする。
- 試験の問題の種類及び解答時間は、次のとおりとする。
| 問題の種類 |
解答時間 |
配 点 |
I 基礎科目
科学技術全般にわたる基礎知識を問う問題 |
1時間 |
15点満点 |
II 適性科目
技術士法第四章の規定の遵守に関する適性を問う問題 |
1時間 |
15点満点 |
III 共通科目(2科目選択)
技術士補として必要な共通的基礎知識を問う問題 |
2時間 |
40点満点 |
IV 専門科目
当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識を問う問題 |
2時間 |
50点満点 |
- 受験者が解答するに当たっては、計算尺、電子式卓上計算機(四則演算、平方根、百分率及び数値メモリのみ有するものに限る。)等の使用は認めることができるが、ノート、書籍類等の使用は禁止する。
試験の実施日程等は、次のとおりです。
3)受験申込書等の配布
「受験申込書」及び「受験の手引」は、平成21年6月1日(月)から配付。
(社)日本技術士会及び(社)日本技術士会の各支部等でお求めいただくか、郵送により請求して下さい。
4)受験申込受付期間
- インターネット受付期間:6月1日(月)から6月15日(月)まで。
- 郵送及び窓口受付期間:平成21年6月16日(火)から7月3日(金)(土曜日・日曜日を除く。)
受験申込書類は社団法人日本技術士会あて書留郵便(7月3日(金)までの消印のあるものまで有効)で送付するか又は同会へ持参すること。
5)試 験 日
平成21年10月12日(月・祝日)
試験方法等は、平成22年度も同様に行われると予想されます。試験日等も同時期に実施されると思われます。
3.技術士第二次試験実施概要(平成22年度は未発表)
平成19年度から、第二次試験の試験方法が大きく改正されました。
改正点を踏まえ、「平成21年度技術士第二次試験実施大綱」(平成20年12月24日発表)では以下のように定められました。
1)技術士第二次試験の実施について
- 技術士第二次試験は、機械部門から総合技術監理部門まで21の技術部門ごとに実施し、当該技術部門の技術士となるのに必要な専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するか否かを判定し得るよう実施する。
- 試験は、必須科目及び選択科目の2科目について行う。
出題に当たって、総合技術監理部門を除く技術部門における必須科目については当該技術部門の技術士として必要な当該「技術部門」全般にわたる論理的考察力と課題解決能力について、選択科目については当該「選択科目」に関する専門知識と応用能力について問うよう配慮する。
総合技術監理部門における選択科目については、総合技術監理部門を除く技術部門の必須科目及び選択科目と同様の問題の種類を問うこととし、必須科目については、「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力を問うこととする。
試験の程度は、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計等の業務に従事した期間が4年等であることを踏まえたものとする。
- 筆記試験(必須科目、選択科目)及び口頭試験を通して、問題作成、採点、合否判定等に関する基本的な方針や考え方を統一するよう配慮する。
2)技術士第二次試験の試験方法
(1) 筆記試験
- 筆記試験は、必須科目については、総合技術監理部門を除く技術部門においては記述式により行い、総合技術監理部門においては択一式及び記述式により行う。また、選択科目については記述式により行う。
- 筆記試験の問題の種類及び解答時間は、次のとおりとする。
(総合技術監理部門を除く技術部門)
| 問題の種類 |
解答時間 |
配 点 |
I 選択科目
「選択科目」に関する専門知識と応用能力 |
3時間30分 |
50点満点 |
II 必須科目
「技術部門」全般にわたる論理的考察力と課題解決能力 |
2時間30分 |
50点満点 |
(総合技術監理部門)
| 問題の種類 |
解答時間 |
配 点 |
I 選択科目
(他の20の技術部門の必須科目及び対応する選択科目のう
ちあらかじめ選択する1科目)
1 選択した技術部門に対応する「選択科目」に関する
専門知識と応用能力
2 選択した「技術部門」全般にわたる論理的考察力と
課題解決能力
|
3時間30分
2時間30分 |
50点満点
50点満点 |
II 必須科目
「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び
応用能力
択一式
記述式 |
5時間30分
(2時間)
(3時間30分) |
50点満点
50点満点 |
※既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者は、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目が免除される。
- 受験者が解答するに当たっては、計算尺、電子式卓上計算機(四則演算、平方根、百分率及び数値メモリのみ有するものに限る。)等の使用は認めることができるが、ノート、書籍類等の使用は禁止する。
(2) 口頭試験
- 口頭試験は、筆記試験の合格者に対してのみ行う。
- 筆記試験合格者には、総合技術監理部門以外の技術部門については「専門とする事項」に関する技術的体験論文(図表等を含め3,000字以内でA4用紙2枚以内とし、白黒とする。)を口頭試験前に提出させる。
なお、総合技術監理部門については、選択科目の「専門とする事項」及び必須科目の「総合技術監理部門」に関する技術的体験論文(それぞれについて図表等を含め3,000字以内でA4用紙2枚以内とし、白黒とする。)を口頭試験前に提出させる。
但し、選択科目が免除される者については必須科目についての技術的体験論文のみを提出させる。
口頭試験は、技術士としての適格性を判定することに主眼をおき、筆記試験の繰り返しにならないように留意する。
試問事項及び試問時間は、次のとおりとする。
(総合技術監理部門を除く技術部門)
| 試問事項 |
試問時間 |
配 点 |
| I 受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容と応用能力 |
全部で
45分 |
40点満点 |
II 必須科目及び選択科目に関する技術士として必要な専門
知識及び見識 |
40点満点 |
| III 技術士としての適格性及び一般的知識 |
20点満点 |
(総合技術監理部門)
| 試問事項 |
試問時間 |
配 点 |
I (選択科目に対応)
I 受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容と応用能力
II 選択した技術部門の必須科目及び選択科目に関する
技術士として必要な専門知識及び見識
III 技術士としての適格性及び一般的知識 |
全部で
45分 |
40点満点
40点満点
20点満点
|
II (必須科目に対応)
I 受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容と応用能力
II 必須科目に関する技術士として必要な専門知識及び見識
III 技術士としての適格性及び一般的知識 |
全部で
30分 |
40点満点
40点満点
20点満点
|
3)受験申込書等の配布
「受験申込書」及び「受験の手引」は、平成21年4月1日(水)から配布。
(社)日本技術士会及び(社)日本技術士会の各支部等でお求めいただくか、郵送により請求して下さい。
4)受験申込受付期間
★インターネット受付
インターネット受験申込受付期間:4月1日(金)から4月16日(木)まで。
★郵送及び窓口受付期間:
平成21年4月17日(金)から5月7日(木)(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
受験申込書類は、社団法人日本技術士会あて書留郵便(5月7日(木)までの消印のあるものは有効。)で送付するか又は同会へ持参すること。
5)試験日等
- 筆記試験日
総合技術監理部門の必須科目:平成21年8月1日(土)
総合技術監理部門を除く技術部門及び総合技術監理部門の選択科目:平成21年8月2日(日)
- 筆記試験合格発表:平成21年10月27日(火)
- 技術的体験論文提出期間(筆記試験合格者のみ):10月27日(火)〜11月9日(月)
- 口頭試験(筆記試験合格者のみ):平成21年12月4日〜平成21年1月20日のうちのあらかじめ受験者に通知する1日
- 口頭試験合格発表:平成22年3月5日(金)〔予定〕
試験方法や、試験日等のおおよその時期は、平成22年度もほぼ同様に行われると思われます。
第一次・第二次の試験日程等は平成21年度の日程ですので、平成22年度の日程発表に合わせてご確認ください。
4.過去3年間の第二次試験結果と新試験の攻略法
過去3年間の第二次試験結果を次表に示します。
試験方法が改正される以前の平成18年度と比較して、改正後の平成19・20年度の試験結果は、部門ごとにばらつきはあるものの、受験者数は増加傾向にあるのに反し、全体的には次第に厳しい合格率となっております。
特に、受験者数の多い建設部門の合格率の低いことが影響しているようです。
また、表では筆記試験・口頭試験を通しての合格率を示しておりますが、以下に筆記試験と口頭試験それぞれの全体結果を示します。
筆記試験での合格率は、18年度では17.8%に対し、19年度では19.6%、20年度では18.8%と、わずか1〜2%、従来試験よりも上がっただけの結果でした。
従来試験においては、筆記試験で技術的体験論文及び必須科目の択一式問題が課せられておりました。さらに試験時間も、必須科目(択一式含む)と選択科目あわせ4時間で解答しなければなりませんでした。現在では、必須科目・選択科目の試験時間をあわせると6時間が与えられているのですから、従来試験がいかに大変厳しいものであったことがおわかりになるかと存じます。このことを考慮すると、新試験における筆記試験は、従来以上に高いレベルを要求する厳しい試験になった、ということがいえましょう。
一方、口頭試験における合格率(筆記試験合格者数に対する口頭試験合格者数の割合)は、18年度では91.3%であるのに対し、19年度は82.0%、20年度は83.4%と、新試験では明らかに従来試験に比べて厳しい結果となっております。
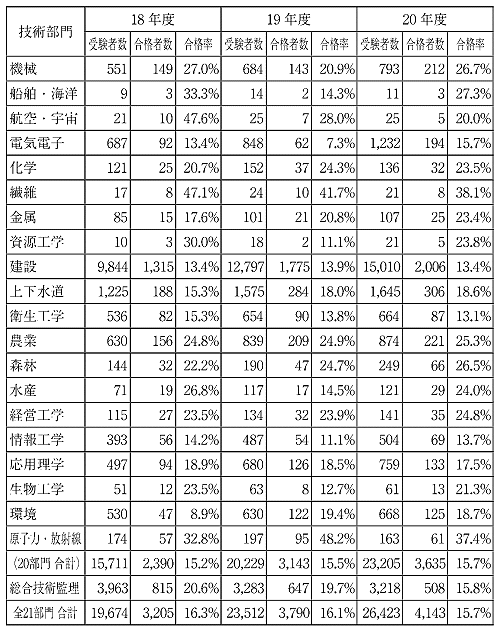
平成18〜20年度 技術士第二次試験部門別結果
上記のような結果になったことは、以下のようなことが要因ではないかと推察されます。
- 筆記試験の問題内容について、選択科目では「専門知識と応用能力」が、必須科目では「論理的考察力と課題解決能力」が要求されることとなったため、付け焼刃的な学習では対応できなくなった。
- 口頭試験においては、筆記試験合格発表後から短期間内に技術的体験論文を提出しなければならないため、事前に準備をしていない受験者は不十分な論文を提出せざるを得ず、口頭試験での評価に影響を及ぼしたと思われる。また、受験申込時に、技術的体験論文の内容を検討しないまま「選択科目」や「専門とする事項」を安易に決めたため、それらの内容と論文内容が一致せず、厳しい結果を招いた受験者もいたと思われる。
- 20年度筆記試験が19年度より厳しい結果になったのは、試験形式が変更になったばかりの初年度よりも、2年目ということでさらに「応用能力」や「論理的考察力と課題解決能力」が要求される問題へと、設問内容が高度になったと考えられる。
逆に、20年度口頭試験が19年度よりも合格率が高くなったのは、新試験についての情報を得ることができたため、新試験初年度よりも事前対策が行えた結果と思われる。
以下、新試験に対しての攻略法のヒントをお伝えします。
筆記試験においては、前述のように、「応用能力」、「論理的考察力」、「課題解決能力」が要求されることになりました。
単に、参考書の丸写しのような答案では、合格に至ることができません。
まず、新試験の問題内容を知ることが必要です。
平成19年度以降の試験内容については、弊社で発行しております『平成21年度版技術士第二次試験問題集』等でご確認ください(『平成20年度版』、『平成19年度版』もございます)。
同書で、受験予定の部門はもちろんのこと、直接ご自身が受験しない部門についても、問題内容に目を通すことをお勧めします。技術分野が独立して存在することはありません。関連分野の技術動向をチェックすることで、広い視野を身につけることができますし、22年度の出題を予想する際のヒントにもなるでしょう。本書で、「応用能力」、「論理的考察力と課題解決能力」とは何かをよく理解していただきたいと存じます。
さらに、それらの問題に対する解答例として、弊社の『平成21年度第二次試験解答事例集』、『平成20年度第二次試験解答事例集』、『平成19年度第二次試験解答事例集』をご覧になってください。新試験攻略のバイブルともいうべき、受験者必携の書籍です。
また、新試験の口頭試験対策としては『口頭試験マル秘対策』をぜひお読みください。多くの受験者による新口頭試験の復元、さらには技術的体験論文の例も複数掲載しているほか、各事例に対しベテラン技術士が解説を加えております。
これから口頭試験を受験される方はもちろんのこと、技術士試験受験申込前の時点から読んでいただきたい書籍です。
試験方法の改正によって、技術士試験はさらに難関なものになりましたが、逆にいえば、受験者の応用能力等を確認することにより技術士としてふさわしいかどうかを見極める、より適切な試験になったともいえましょう。
試験に合格するためには、まず、「技術士に絶対なるぞ!」という強い決意が必要です。
そして、その決意を試験まで継続することにより、試験合格への最短距離を歩むことができます。
「応用能力」、「論理的考察力」、「課題解決能力」は、一朝一夕では身につきません。
普段の業務や日常生活の中で、「技術士」を意識し、行動することで培われていきます。
今、この日から決意してください。「なるぞ!技術士 !!」と。
| |