





|
2002.10【特集記事−本誌編集部より−】 不適合管理、是正処置、予防処置をいかに活用するか トータルISOで実力をつけリスクヘッジを |
||
|
ISOを経営に取り込み、マネジメント力を強化しようというトレンドはここのところ、とみに強まっている。 マネジメントとはプラン、ドゥ、チェック、アクションを上手に機能させ、スパイラルアップさせていくことであり、ここに「継続的改善」、そしてこれを管理する手腕が問われ、トップの方針を高らかに歌い上げるところでもある。 ●不適合を見つけるためになかでも「不適合管理、是正処置、予防処置」は重要項目である。この不適合の定義は
さて、入手したら、すぐに社長へメモやメールなどのバイパスコミュニケーションにより、情報の真偽や深さを問わず、連絡することをシステムとして確立しておく必要がある。 最近は3.の内部告発が世間の耳目をそばだたせることが多い。だが、こうした社内システムを確立しておけば、いきなり外部への告発があり、企業が対応に戸惑い、その姿がマスコミを通してすべてさらけ出され、イメージ低下、商品競争力を落とし、企業の存続さえ危うくするといった事態は避けられるはずだ。 某社では「内部告発、多いに結構。だが、その第一報は私にしてくれ」と社長自らがオープンな社風づくりを心がけているという。 ●不適合発生原因は身近にところで、この不適合発生原因をよくよく調べてみると
これらは品質、環境、OH&Sすべてにかかわることが多く、処置・対策を一本化することで、より広く改善効果が期待できる。 たとえば、職場の環境美化。これは5Sに分類されるが、いくら5Sをやっても、切粉の発生源を解決なくして成立しない。この発生源対策は品質にもつながり、従業員の労働安全につながる。一方、切粉そのものの削減は環境保全の立場からも推進されるべき行為である。一つの改善が多くの効果を生む。タンクの不十分な洗浄に端を発した乳業メーカーでは清掃、清潔の欠如(1.)、また、この確認作業の欠如(2.)、そしてなんといっても組織の腐敗(3.)があったとされても仕方あるまい。職場の環境はどうだったのか、ごみ処理や産業廃棄物の適性処理は行われていたのだろうか。 ISOは取得することが目的ではない。経営システムに組み込んで活用してこそ、意義がある。攻撃は最大の防御といわれるが、ISOの活用は効率アップとリスクヘッジの最大のツールといえよう。 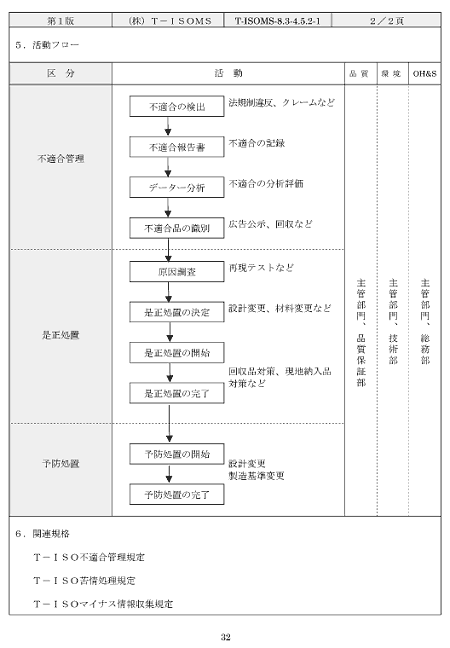
|


